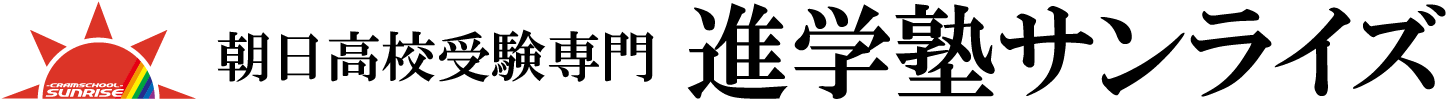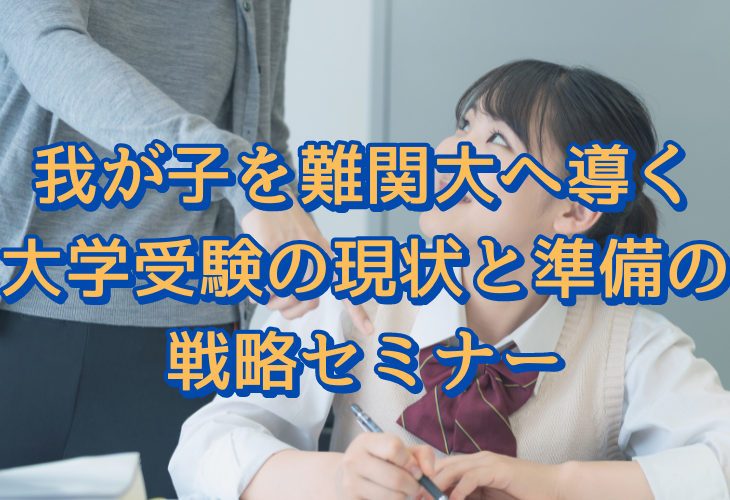なかなか勉強に取り組めない・・・と悩んでいる声を聞くことがあります。
何度も声掛けをしても効果がないとあきらめている人も多いのではないでしょうか。
「うちの子は集中力がない」
これについては、全くそうは思いません。
そういう子を指導した時に、他の子とほとんど変わらず集中して勉強している姿を何度も見てきました。
なぜ集中できるのか、集中力を身につけるにはどうすればよいか。
以前に塾で「集中力アップ講座」をしていた経験も踏まえて、なぜ集中できないか、その原因を挙げていきたいと思います。
少しでもヒントになればと思います。
視界に邪魔なものが入ってくる
人が集中した状態で知的活動を行っている際、何かしらの邪魔が入ると、再び集中した状態に戻るまでに23分もかかるそうです。
頻繁に邪魔が入るような環境にいると、子どもの脳にある実行機能が阻害されます。
子どもたちの周りは、楽しい刺激でいっぱいです。
ゆえに、頭の中は雑念に占領されやすくなっているのです。
効率的な学習や脳の発達にとっては、脳が集中しにくい環境にあるのです。
勉強するときには、視界に無駄なものが入ってこない環境が必要です。
勉強に関するものだけ、誘惑も一切なし。
家の中、子ども部屋、机の上などを見てどうでしょうか?
脳は、無駄なものからも無意識に情報を取り込み、エネルギーを消耗し、疲労します。
家庭で勉強できる環境にありますか?
ルーティンがない
ルーティンとは、いつもきまってやる動作などのことですが、スポーツ選手などが普段の練習からルーティンによって「集中するためのスイッチ」を入れています。
そういった「ルーティン」って家での勉強でありますか?
これは、心理学的にも効果があることが明らかになっており、勉強にも活用できます。
例えば、塾では幼児・低学年の子にもルーティンを決めています。
「塾に来たらまず、〇〇をする」というルールにしているんです。
ルールといっても、規則ではないので破っても罰則はありませんけどね。
毎回、子どもは当たり前のようにしているので気付いていませんが、実は、自然とルーティンが染みついているのです。
「スイッチ」入れていますか?
長時間集中できない
子どもが集中できる時間は、幼児~小学校低学年の場合は「年齢+1分」程度、高学年から中学生でも「15分」程度だと言われています。
非常に短いと感じますよね?
そもそも子どもは長時間集中することができないのです。
家で1時間机に向かっているが、実際に勉強している時間は半分ほど・・・というのも納得ですね。
「なあんだ、結局それか」
ではなぜ、長時間も塾で勉強できるのでしょうね。
長時間勉強させるには、工夫が必要になります。
休みがない
ずっと部屋にこもらせて勉強させても、集中力が続かないのは当たり前です。
では、家で勉強している時に、「タイムアウト」を取っていますか?
勉強の合間に休憩を入れて脳を休めることは、学習効率や集中力アップに必要です。
家ではもちろん休憩を取りまくっていると思いますが、「休みがない」というのは塾で言えることかも。
某塾では授業中に休憩がないそうですが、うちの塾では始業時間だけでなく、休憩も自由です。
おやつ休憩、食事休憩は当たり前です。
読書休憩や教具などで遊ぶ休憩もあるかな?
集中力が切れるタイミングも人それぞれなのですから、60分、90分ぶっ続けというのも無理でしょうし、同じタイミングで休憩を取れというのもおかしいと思うのです。
飲食禁止
これも、学校や塾に限るでしょう。
脳の80%は水でできています。
脳の働きを高めるために水分を補うことは大切です。
勉強の前に水を飲むと集中力と記憶力の向上が見られるという研究結果もあります。
塾に水筒を持っていくのって今は当たり前なんですかね?
もちろん、うちの塾では水筒、お菓子、お弁当は持ち込みOK。
食べながら、飲みながら勉強する子はいませんが、休憩の際には水分補給、エネルギー補給をしています。
入塾したばかりの生徒「え?授業中にお茶飲んでいいんですか!?」
これ、よく言われます。
あの~・・・。
昭和の部活ですか?(笑)
家での勉強は必須?
家での勉強がなかなか難しいというのは原因があるわけです。
どうでしょう?
改善できそうなことがありましたか?
うちの塾の生徒は、「家では勉強しない」と割り切って、塾で学校の宿題もやって帰っている子が多いです。
そう考えるのも一つの手ですよね。
共働きなどで、学童保育施設に預けられている方もいると思います。
サンライズは、「学童塾」とは表に出していませんが、学校帰りに直接塾に来て、授業が始まるまでに学校の宿題をしたり、おやつを食べたりしています。
授業が終わった後も、お迎えが来るまでの間に、軽食を食べたり、本を読んで待っています。
平日は、15時から22時まで塾を開けていますので、その間でしたら塾にいても構わないとしています。
特に、伊島小学区、津島小学区には学童が少ないので、大歓迎ですよ。
子育てのヒントが見つかる保護者セミナー