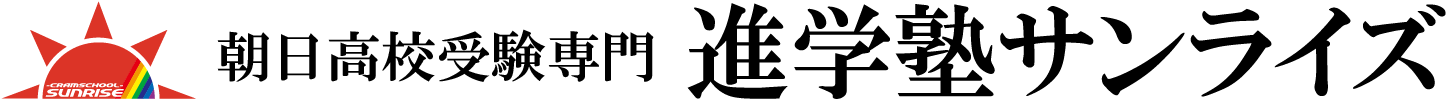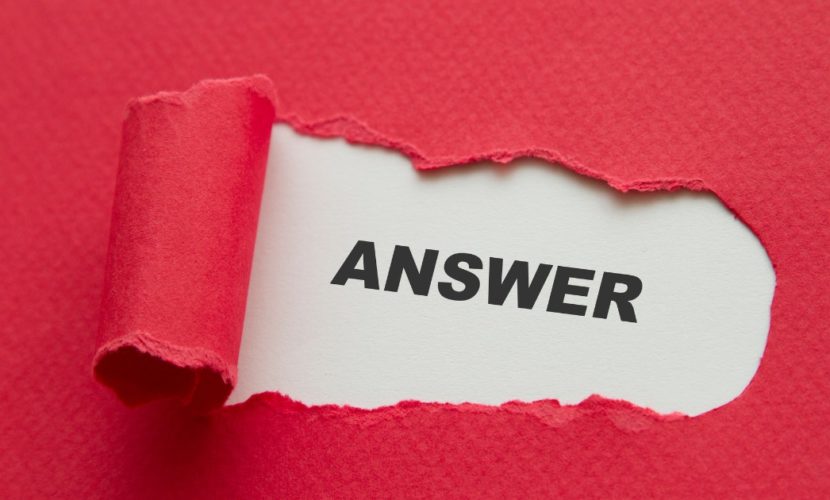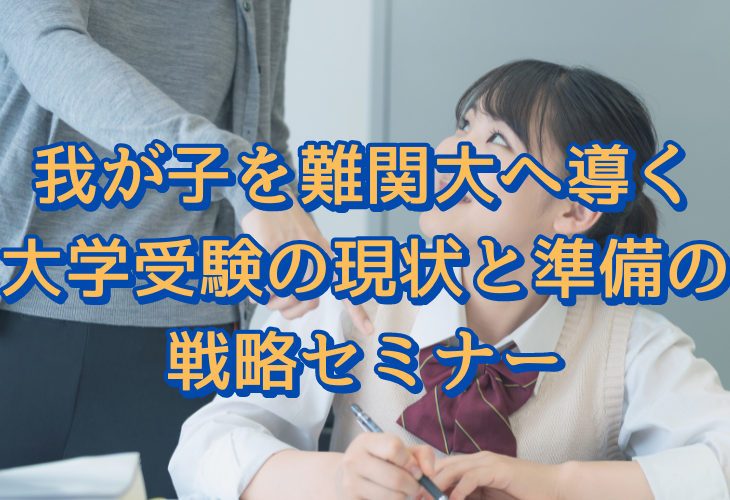サンライズでは、小3から自分で答え合わせをさせます。
自分で答え合わせができない子というのは、間違っているのに正解としている場合が多いです。
でも、本当は「合っているか、間違っているか、よくわからない」というのが原因のようにも思います。
これでは、きちんと勉強しているとは言えません。
自分でできないならと、大人が答え合わせをやってしまうと、いつまでも自分で答え合わせができないでしょう。
原因はそこではないから。
間違えているのに〇をしたところを、「なぜこれは〇なのか?」と問うとよいでしょう。
理解していない子や、乱暴な丸付けをしている子は、答えられないはず。
手助けするのではなく、できるように導いてあげた方が、子どものためになるでしょう。
本当に自分で答え合わせができる子って少ないですよ。
昔、中学生の理科の問題で、その学年全員が答えに「オ」を選んで〇にしていました。
「オ」で〇にしている子や、他の選択肢を選んで「×」にして、赤で「オ」と書いている子もいました。
「なぜ?」と聞くと、全員、「答えがそうなっていたから」と答えたのです。
塾長ブチギレ。
さて、なぜブチギレたのか?
実は、その問題の選択肢は、ア~エまでしかなかったから。
(解答が間違っていたのです。問題集ではよくあることですね。)
答えを写して〇にしたんでしょうね?
自分の答えが合っているのに、違うと思ったんでしょうね?
どちらにせよ、ブチギレです。
(叱るときは、本気で怒っているということを相手に伝わるようにすべきです。暴力はダメ!)
答えを写している子は論外ですが、自分の答えが合っているのに、×とした子は、「なぜ違うのか?」を考えていないことがわかります。
選択肢を見れば、「あれ?オがない・・・」と気づくはず。
こういった積み重ねが勉強の効率の妨げになっていることを、早く気づかせてあげないといけません。
「なぜ?」と考える習慣づけは、自立学習には必要不可欠です。
問題の解き方一つで成績の伸び方が変わる
成績が伸びている子と成績が伸びない(下がる)子の差は、問題の解き方を見ていると違いが表れています。
そもそも、宿題をしない子は、その分演習量が少ないので、わからなくなっていくのは当然です。
ここでは、勉強をしている=問題を解いているにも関わらず、伸びない子の特徴を述べたいと思います。
一般的には、
①問題を解く⇒②答え合わせをする
の流れですね。
小学校高学年くらいになれば、答え合わせまで自分でできる子もいるでしょう。
実は、多くの子は、この答え合わせがきちんとできないために、なかなか学力が伸びないです。
きちんとできない例をいくつか挙げます。
1.答えが間違っていたら、赤で答えを写す“だけ”
入塾したばかりの子に多く見られるのが、このやり方です。
答えを赤で書いて、そのままにしてしまっているんですね。
「じゃあ、なんでこの答えになるの?」を聞くと、大抵は、答えられません。
できる子は、間違えた問題は、もう一度自力で解いてみるか、分からなければ質問したり、解説を読むことによって、理解をし、もう一度解きます。
「決して答えを見ながら写す」ということはしません。
2.答えが間違っているのに、○をする。
きちんと勉強しているのにテストで結果が出ない子は、間違ったことを覚えている可能性があります。
英語のスペル、漢字のミスなど、自分では合っていると思い、○をしてしまうのです。
自分の答えが間違っているかも・・・と疑いながら、答え合わせを慎重に行う必要があります。
まだ答え合わせに慣れていない子によく起こる現象です。
3.一度解くだけで、間違えた問題を復習しない。
間違えた問題が、その時は理解できたとしても、しばらく経つと忘れていることだってあります。
間違えた問題ができるようになることで、成績が伸びるのですから、解けるようになるまで、きちんと復習をしましょう。
4.宿題を出すことが目的になり、問題をいい加減に解く。
宿題をしなくてはいけない、と思っている子は、なかなか伸びないでしょう。
宿題の目的がよく分かっていない、もしくは納得していないからです。
ですから、つじつまを合わせるために、さもやっているかのように見せて、問題を飛ばしていたり、答えを写しているだけだったりするのです。
もちろん、これでは成績が伸びることはありません。
5.調べたり、人に聞いたりして解けた問題が、自分で出来た気になっている。
初めて勉強する内容は、誰しも分からないことがあります。
分からなかったら、調べたり、質問して解決しますよね。
その問題も、問題にチェックを入れて、後で復習をすると良いでしょう。
効率良く勉強するためには、以上のことがきちんとできていることが前提です。
サンライズでは、入塾したての子には、まず、このような勉強の仕方をみっちりと教え込みます。
それが、成績を伸ばす最短の方法だからです。