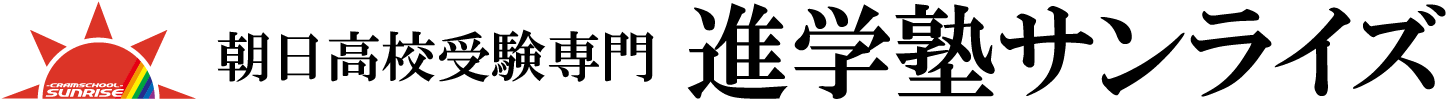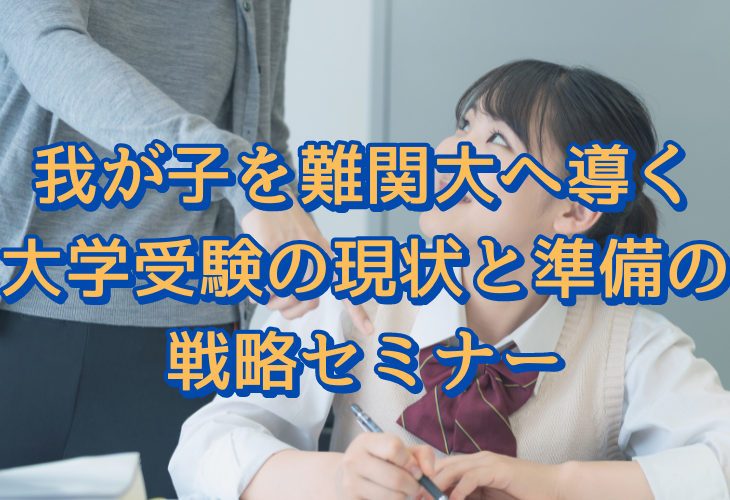多くの学校では、入試で面接があります。
練習していないと、面接で質問されてもうまく答えることはできません。
ここでは、よく聞かれる質問内容の例とその意図や面接時のポイント、大原則、対策方法について説明します。
面接では主に次のような内容を聞かれます。
あらかじめどう答えるか考えましょう。
よく聞かれる10の質問
質問の具体例として10個挙げると、以下のような内容です。
- 「受験番号と氏名を教えてください。」
- 「この高校(本校)を選んだ理由を教えてください。」
- 「あなたの長所と短所(性格)を教えてください。」
- 「中学校3年の生活の中で一番頑張ったことは何ですか。また得たものは何ですか。」
- 「この高校(本校)に入学したら(高校を卒業したら)したいことはありますか?その理由は?」
- 「ご両親(友達)はどんな人ですか?」
- 「あなたの得意(苦手)科目はなんですか?その理由は?」
- 「あなたの趣味や特技を教えてください。」
- 「最近のニュース(新聞)で印象に残ったものを教えてください。」
- 「この高校(本校)の校風は?」
質問で聞かれる内容は概ね決まっています。
それぞれの質問の意図とポイントを説明します。
面接における質問の意図とポイント
その1 客観的事実の説明
・「受験番号と氏名を教えてください。」
ここがポイント:客観的な事柄について面接官の目を見て、大きな声ではきはき答えられるか。
その2 志望動機の説明
・「この高校(本校)を選んだ理由を教えてください。」
ここがポイント:きちんと高校を調べて理解したうえで志望しているか。
その3 自己評価
・「あなたの長所と短所(性格)を教えてください。」
ここがポイント:自分のことについて、きちんと自己評価できているか。
その4 中学生活について
・「中学校ではどんなことをがんばりましたか?」
ここがポイント:ただ漠然と中学生活を過ごしていないか。 ※漠然(ばくぜん)=なんとなく
その5 目標について
・「この高校(本校)に入学したら(高校を卒業したら)したいことはありますか?」
ここがポイント:目標は「合格」ではなく、「合格後」にあるか。
その6 友達や家族について
・「ご両親(友達)はどんな人ですか?」
ここがポイント:自分以外の人についてどんな見方をしているか。
その7 勉強について
・「あなたの得意(苦手)科目はなんですか?その理由は?」
ここがポイント:科目の特性を理解しているか。さらに自分の長所や短所とからめて把握できているか。苦手なのを人や環境のせいにしていないか。
その8 趣味や特技について
・「あなたの趣味や特技を教えてください。」
ここがポイント:通常、趣味や特技の内容(分野)は問われない。取り組み方が確認される。※お坊ちゃん・お嬢様学校で聞かれた場合などは別
その9 ニュースや新聞について
・「最近のニュース(新聞)で印象に残ったものを教えてください。」
ここがポイント:ニュースを見ているか。どのような事件(事柄)に関心があるのか。
その10 基本的な知識の口頭での説明
・「縄文式土器と弥生式土器の大きな違いはなんですか?」
ここがポイント:各科目の基本的な知識に関して、口頭で説明できるか。
基本質問から派生した質問内容
面接で問われるほとんどの質問は、ここにあげた「10の基本質問」から派生します。
例えば「その1 客観的事実の説明」の場合。
- 「受験番号と氏名を教えてください。」 (基本質問)
- 「あなたの所属している中学校名と校長先生の名前を教えてください。」 (派生)
- 「あなたのクラス番号と担任の先生の名前を教えてください。」 (派生)
これらは全て「客観的な事実」の説明です。
言い換えれば「誰が答えても同じ答え方になる。」質問です。
自分に関係ある事柄の正式な呼称を覚えておけば簡単に答えられます。
その他の質問についても、問われ方は違っても問われる内容(ポイント)は大体同じになります。
面接を攻略するための大原則
大原則1 焦らない。慌てない。落ち着いて。
意表をつくような質問をされても慌てないことが大切。
答えに詰まっても「分かりません。」と言わずに「少し考えさせてください。」と言いましょう。
なんでもすぐに答えようとする必要はありません。
大原則2 しゃべるときは相手の目を見て、普段より少し大きな声で。
普段すごく小さい声で話す人は、めいっぱい声を出しましょう。
声を大きくするというのは意外に重要です。
良いことを言っていても声が小さいと説得力がありません。
大原則3 高校のことはしっかり調べておく。
基本的なことは何を聞かれても答えられるようにしておきましょう。
例えば建学の由来(精神)・校長の名前など。
これらは全く聞かれないこともありますが、めげないこと。
大原則4 ウソはつかない。
ウソは厳禁。
面接官は何人もの学生を見ていますから、沢山の質問の中で必ずばれます。
大原則5 思ったことを言うのではなく、面接官(高校)がどういう答えを求めているか考えて答える。
これを読んで「ん?それは、ちょっと違うんじゃないの?」と思うかもしれません。
大原則4で「ウソはつかない」と言いました。
自分のことを正直にしゃべるのが面接じゃないの??
実はこの大原則5がこの「最強の面接術」の最大のミソです。
「高校受験の面接」では、自分のありのままを語るのが正攻法です。
ですから、もともとまじめで成績も良く、面接を無難に乗り切れば合格できる人は、本当のことだけ言えばよいです。
ちなみに「企業に入社する時の面接」で、自分をありのままに語る人はまず落ちますので、将来はご注意を。
一方、「正攻法で乗り切ればOK」ではない受験生も多いと思います。
そこで、ここでは面接で得点を稼ぐための秘策を教えます。
それは・・・「相手(面接官や学校)の望む答えを用意する。」です。
これを意識して面接を受けるのと、しないで受けるとでは天と地ほどの違いがあります。
先に注意しておきますが「ウソ」をついて相手にあわせるのは禁物です。
大原則4に違反します。
例えばやってもいない「生徒会の役員」「部活動」「奉仕活動」などを、やったことにするなどは駄目です。
ではどうすればいいのか。
まず志望する高校について徹底的に調べます。
「そんなこと普通の受験生は知らないよ」というところまで調べましょう。
それだけで一歩リードですが、そうして調べていくと「高校の特色」が見えてきます。
「しっかりと自主的に行動できる生徒」・「規則を守って行動できる生徒」・「新しいことにチャレンジする生徒」など、高校によって求める生徒像が違います。
特に私立高校は分かりやすいでしょう。
調べがついたら、あとは高校の望む姿に合わせて答え方を考えるのです。
過去の事実について異なることを言えばウソになりますが、自分の希望や将来のことを、相手に合わせて考えることはウソではありません。
なにしろこれからの事なんですから。
「志望校に合わせろと言われても具体的にどうすれば・・・。」という人のために面接での答え方の例をあげておきます。
ここでは「10の基本質問」の「その2 志望動機の説明」に対する、高校種類別の答え方(自己PR)を考えてみましょう。
「しっかりと自主的に行動できる生徒」を求める高校の場合
質問 「この高校(本校)を選んだ理由を教えてください。」
回答例
私は自分でものごとを決めて行動することが、成長につながると考えています。(←※ポイント1)
中学校では、自分で決められることの範囲はあまり多くなかったのですが、高校ではそれが広がると思います。
特に○○高校は校是(こうぜ)にも「自主自律」の文言があり、高校見学の際にも生徒の自主性を重んじていると先生方が仰っていました。
そういった○○高校の校風は私にぴったりであると思い志望しました。
「規則を守って行動できる生徒」を求める高校の場合
質問 「この高校(本校)を選んだ理由を教えてください。」
回答例
私は秩序を重んじる性格です。
例えば学校の清掃の時間では、他の人が早くに掃除を止めてしまっても、チャイムが鳴るまでしっかりと掃除をしました。(←※ポイント2。)
また、放課後は寄り道をすることなく、まっすぐ家に帰って鞄を置いてから出かけるようにしていました。
こうした性格もあって、わたしは多くの友人からの信頼を得ています。
○○高校は建学の精神にも「規律・秩序・礼儀」を重んじるとあります。
また、学校見学では先生方や先輩の丁寧な振る舞いを拝見して感動いたしました。
それが○○高校を選んだ理由です。
どうですか?説得力があると思いませんか?
過去の自分の行動の中で「志望校が好みそうな事柄」を選んで引き合いに出します。
さらに「志望校についてしっかり調べていますよ」というところを理解してもらうために、志望校の特色について具体的に例をあげて話します。
そしてその二つを掛け合わせて「だから、○○高校を選びました。」と結びます。
回答例のポイント
さて、回答例中にあった二つのポイントの違いは分かりましたか?
※ポイント1:主観的な事柄(客観的な事実ではない)から、本当に思っていなくても良い。
※ポイント2:客観的な事実だからウソは駄目。
ポイント1のような「主観的な事柄」は言ってみれば「本人がどう思うか。」です。
これは、高校に入ってから変えることもできますし、3年間も通えばおのずと校風に染まってきます。
ですから、ある程度は実際と違っても問題ありません。
それより「高校(面接官)が求める答え方」をすることが大切です。
ただし、高校の求める生徒像と自分の性格が180度(全く)違う場合は、そもそもその高校を志望するべきではありません。
仮に合格して入学しても3年間ギャップに苦しむことになります。
ポイント2は過去の客観的かつ具体的な事実です。
多少の誇張くらいなら許されますが、それ以上のことはNG(駄目)です。
面接官に矛盾をつかれて、ウソがばれたりしたら大変なマイナスになってしまいます。
客観的な事実に関しては、とにかくウソは禁物です。
面接に向けて – 対策と練習

誰かに面接官役をお願いして、練習してみましょう。
これは家族だと照れてしまうし、お互いのことを知りすぎているため難しいと思います。
学校の先生や近所の人や親戚の人に頼めると良いですが、適当な人がいなければ家族でもOKです。
落ち着いて丁寧に説明する練習をしよう。
人は普段は想像以上に早口でしゃべったり、略語を使ってしゃべったりしています。
また感情をすぐに顔に出したり、体が動いたりします。
面接でも感情が顔に出るのはある程度は仕方がありませんが、早口や仲間内だけで通用する言葉を使うのはNG。
急に面接仕様にはなれないものです。
週に1回くらいは面接の話し方を練習しておきましょう。
椅子の座り方や服装などは本番と同様に練習しよう。
練習だからと普段着でやったり、こたつに入りながらやっていては意味がありません。
服装と髪を整え、椅子に座って相手の目を見て話す練習をしましょう。
敬語の訓練をしておこう
普段から敬語を使って生活すると良いです。
照れくさいかもしれませんが、練習と割り切ってご両親に対して敬語で話してみましょう。
普段から敬語の人はこれは全く問題ないですね。
質問や答え方を覚えるのではなく、よく考えておこう。
きちんと理解して考えておかないと、質問の仕方が違うだけで答えられなくなってしまいます。
予想外のことを聞かれて焦ってしまう可能性も高まります。
面接で志望校が問わんとするところをよく考えて、自分なりの答えを出しておくことが大切です。
あとは自分に自信を持って!
あなたが面接を見事突破することを祈願します。