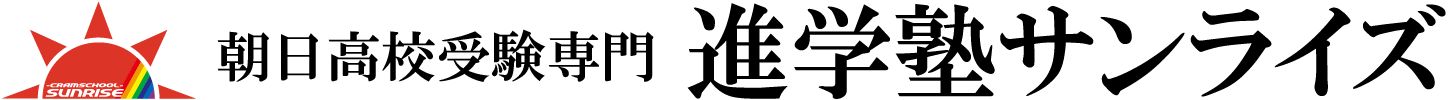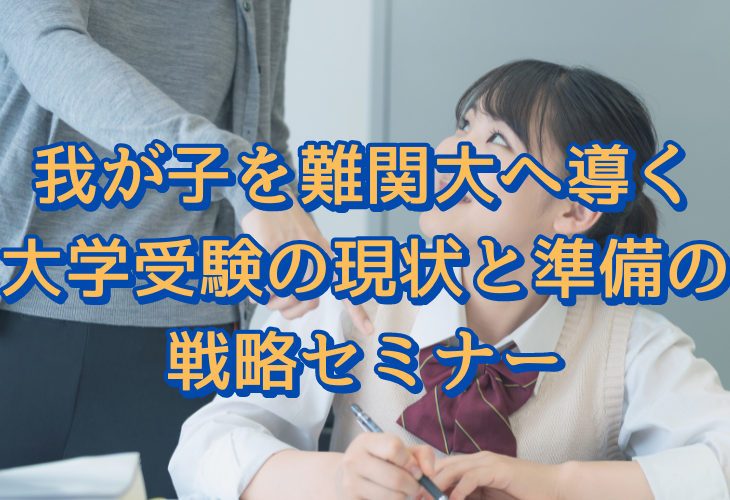先日、質問や相談をする習慣が大切だと書きました。
但し、ちょっと考えてわからなさそうだったら、「先生に聞けばいいや」と自分で考えることを放棄してしまうのは、いけません。
そうなると、「自分で考え、自分で行動する」という主体性がなくなり、「他人に聞いて教えてもらう」「他人に指示してもらわないとできない」という受け身な子、いわゆる指示待ち人間になってしまいます。
社会に出ると、思ったようにいかないことや、どうしたらいいかわからないことはたくさんあります。
そんな困難を乗り越えていくには、単に「何でもわからないことは他人に聞く」だけではダメなのです。
わからないことを一人で考え込まず、他人にアドバイスを求めることも本当に大切なことですが、同時に、「自分で考え、行動する」ことも大切なのです。
ですから、まずは、自分の頭で考え、それでもわからなければ、素直に他人のアドバイスに耳を傾けることができるように、子どもを育てていきたいです。
ちなみに、私が実践していることは、子どもが質問してきたら、「自分はどう思う?」「その質問のどこまでがわかって、どこからわからないの?」などと聞くようにしています。