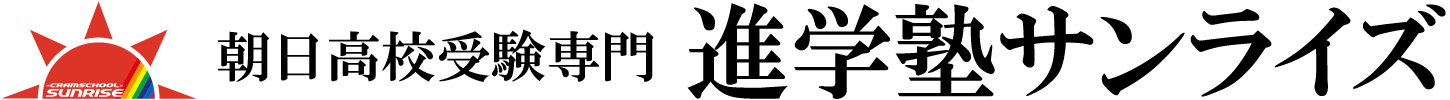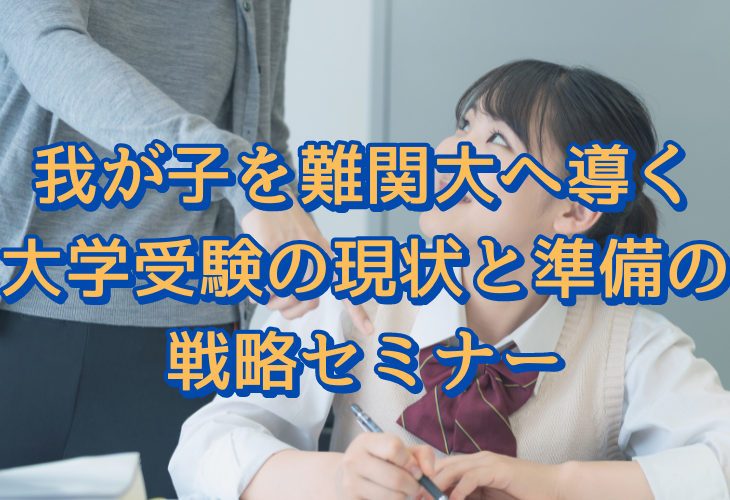地球の未来を考える:温暖化と私たちの生活
地球温暖化は、18世紀末の産業革命以来、進行し続けています。
最近の世界気象機関(WMO)の発表によれば、今後5年以内に地球の平均気温が1.5度上昇する可能性があるとのことです。
この気温の上昇は、日本でも異常気象の原因となっており、農作物への影響も避けられません。
産業革命が資本主義の確立を促し、20世紀にはアメリカ合衆国がその代表格となりました。
しかし、合理主義と大量生産の文化が生み出した”食器を洗うのは時間の無駄だから紙皿、紙コップを使って、そのまま捨てる”という「使い捨て文化」は、今、見直されつつあります。
一日一日を大切に:学習の「使い捨て」をやめる
この「使い捨て文化」は、子どもたちの学習方法にも影響を及ぼしているかもしれません。
学んだことをすぐに忘れ、「テスト週間になると急に詰め込む」という学習法は、長期的に見るとあまり効果がありません。
学校や塾で学んだことを、その日のうちにもう一度振り返る時間を設けることで、学習内容の定着を促しましょう。
それには、例えば、英語なら「助動詞:動詞の意味を補助的に助ける。英語では日本語と違い動詞の前に置く」、数学なら「一次関数:xを決めるとyがただ1つ決まるもの。自動販売機のメカニズム」、地理なら「世界の諸地域をいろいろ習うと、植民地だったところは単一作物(モノカルチャー)なんだと俯瞰しておく」など、学んだ内容を「小見出し」として頭の中で整理することが役立ちます。
愛情を込めて学ぶ:「思いを馳せる」学習法
日本語には「思いを馳せる」という美しい表現があります。
これは、「気持ちを向ける」という意味で、人だけでなく物事に対しても使うことができます。
例えば、「故郷に思いを馳せる」のように使います。
学んだことに対しても、日の終わりに愛情を込めて思いを馳せることで、学習内容がより深く、長期的に記憶に残ります。
これは、単にテストで良い点を取るための勉強ではなく、実生活で役立つ知識として身につけることを意味します。
まとめ
今日の子どもたちが直面している学習課題は多岐にわたりますが、彼らの学習方法を「わかる」から「できる」へと変えることができれば、学びに対する彼らの姿勢も変わるでしょう。
地球温暖化への対策と同じように、学習方法も見直し、改善する必要があります。
毎日の学習を大切にし、学んだことに対して愛情を持って接することで、子どもたちは真の学力を身につけることができるのです。
子どもの学びについて真剣に考える親御さん限定の説明会です。