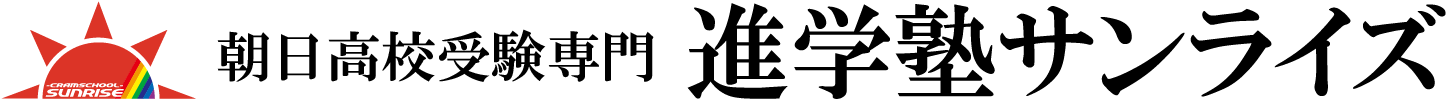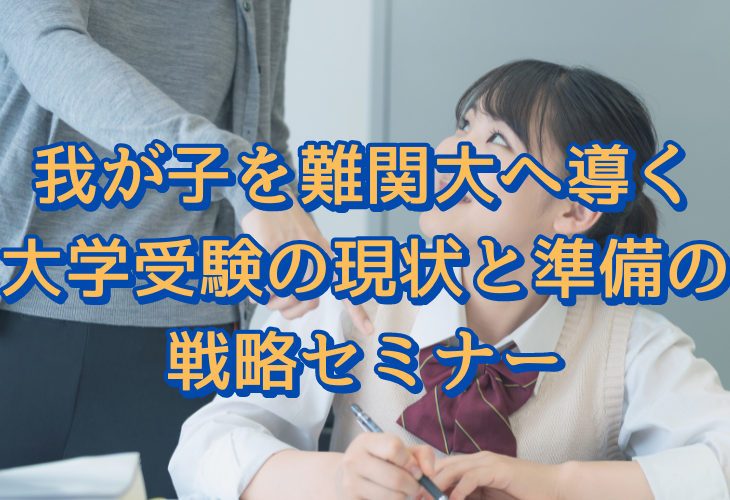先日の記事
について、名門公立高校受験道場でお付き合いのある後藤先生が
以下の記事を書かれていました。
■子どもが賢く成長する親のGood行動トップ10
1.結果のみでなく子どもの普段の頑張り・努力の過程をしっかり見て評価してあげる
2.子どもの過去ではなく、未來の夢・そのために今やるべきことを一緒に語り合う
3.謙遜ばかりせず、場面によっては子どもの良いところをしっかり言葉にして伝える
4.普段の声かけ・適度の目標の設定等で、子どもがやる気になるように仕向けることができる
5.学習計画を子どもが自分で立てられるように協力する。基本的には子どもを信用して任せて、毎日口うるさく点検したりしない
6.勉強と部活や習い事等の両立をできるように協力する
7.常に子どもと会話をきちんとすることを心がける。子どもが気持ちをうまく伝えられない時も、イライラしないでじっくり聞いてあげる
8.子どもが落ち込んでいる時は、デーンと構えて明るく包み込んであげる
9.常に夫婦円満を心がけ、子どもの前で喧嘩をしたりしない
10.子どもは自分とは別個独立の存在だと認識し、親のエゴを押し付けない
確かに、これらを実行するのはかなり大変ですね。
いきなり完璧を目指すのではなく、
少しずつでも意識して子どもと接することで、
プラスの方向に向かいます。