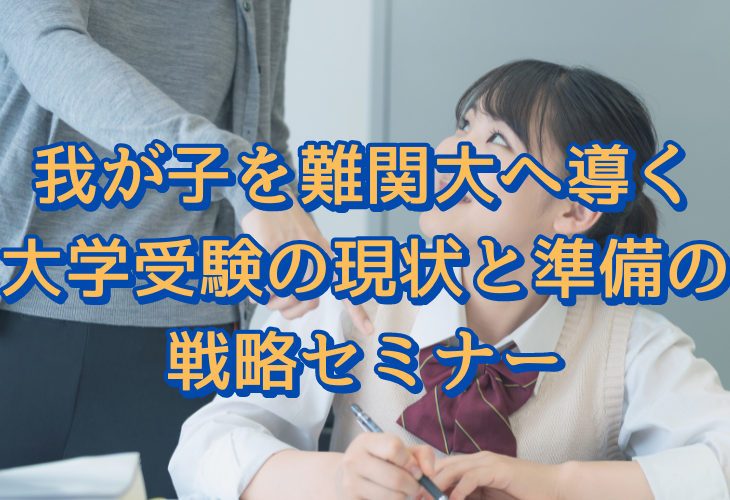子どもの思考力、今と昔の変化
教育の世界では「思考力」の重要性が長年語られてきました。
しかし、最近の子どもたちは基本的な応用力に欠け、簡単な問題も解決できない傾向にあります。
例えば、小学4年生が「入る」の反対語を「入らない」と答えるなど、基本的な国語の理解にも苦労しています。
小学5年生になるとさすがに正答を言えるのですが、対義語に限らず国語全般が苦手分野になっているのは事実です。
これは、言葉と思考力の密接な関係を示しており、親として気をつけるべき点です。
グループワークでの学びの効果
思考力を養うため、私たちの教室では講義形式からグループワークへの移行を試みました。
受動的な講義形式は、集中力が持続せず、板書を漫然と眺める時間が長くなる傾向があります。
数十分の授業の中で本当に意味があるのは5~10分しかない、という説もあるほどです。
そのため、演習中心の授業を行っています。
この方法では、子どもたちが自発的に考え、互いに教え合うことで深い理解が促されます。
特に算数では、チームで問題を解くことで、理解力が向上することが期待されます。
他の子に解き方を説明することで自発的に考えるきっかけとなり、本当の意味での理解が進むようにしました。
これは、学校だけでなく、家庭でも応用できる方法です。
過干渉は思考力の敵
現代の子どもたちの多くは、親の過干渉により自分で考える機会が奪われています。
粘り強くやり抜く習慣がないので、問題を解けないとすぐに答えを求める傾向があり、これは長期的な思考力の育成を妨げます。
似たような問題でも、応用問題が出た時に解けないケースも見られます。
親としては、子どもが自分で考え、解決策を見つける機会を積極的に与えることが重要です。
最終的には、子ども自身が自分の方法で問題に取り組む力を身につけることが育成の目標です。
思考力を伸ばすための親の役割
子どもが自分の思考力を十分に発揮できるよう、親は支援の役割を果たす必要があります。
これには、子どもが自ら学ぶことを尊重し、持ちうる知識を総動員して解き、日頃から自発的に「なぜ?」「どうして?」と疑問を持てるよう促すことが含まれます。
自分から興味を持って調べたり考えたりする力は、親が手伝いすぎると身に付きません。
子どもを信じて見守ってあげる必要があります。
親が全てをコントロールするのではなく、子どもに自由な発想の場を提供することが鍵です。
子どもの自立した思考力を育てる
最終的には、子どもが自立して思考し、問題解決できる力を身につけることが目標です。
これは、幼児期から中学生にかけて、親が子どもを信じ、適切に見守ることで達成できます。
過干渉を避け、子どもが自分で考え、行動する機会を増やすことで、本当の思考力が育つのです。
子どもの学びについて真剣に考える親御さん限定の説明会です。