子どもたちの成長を長期に渡り見守る革新的な学習指導法

岡山の公立トップ校である岡山朝日高校を目指す生徒たちは、その先の難関大学への進学も見据えています。
私自身、大学合格後に塾の講師としてのキャリアをスタートさせてから26年、これらの生徒たちの学習指導に関わってきました。
初めは大学受験生を指導していたので、その頃から「高校生を教えるということはどういうことか」、ひいては、「『高校生を教えるということ』から大学受験の結果を出す、大学受験の結果を出すこと=高校生を教えることである、そのためにはどういう学習指導を行えばよいのか」、それを常々ずっと突き詰めて考えてきました。
そこから、いかに子どもたちを難関大学に合格させるかということを考えた場合には、「高校生になって、どれだけ効率よく勉強できるようにするのか」、その一点だけなんです。
そのためには、高校生自身を教育していく必要もありますが、そこからフィードバックして、じゃあ中学段階で何ができるか、もっと言うと、小学校段階、あるいは幼児の段階で何ができるか、というのを考えていった時に、実は単純に大学受験に合格させるということだけではありません。
もう一つ、中高の6年間、小学校1年からいいますと12年間、小4あたりからだとしても9年間、当塾の場合、幼児から高3生まで指導しておりますから、大学合格までの18年間の人生のほとんど、ということになりますが、その長いレンジで子どもたちの学習を見てあげる立場にある人は、誰なんだ?というところに行きつきました。
それは、やっぱり学校ではないんですね。
高校でもなければ、中学でもない。
一番長く子どもたちに関われるのは、もちろん親なのですが、親以外でとなると、それはやっぱり、塾ではないのでしょうか。
我々塾人でしか成し得ない立場にあるのではないか、そこからもう一つ新しい指導方法、また考え方が見えてきたものがあります。
その長いレンジで子どもたちの学習を見るというのをフランス語でリセというそうで、以後、リセ教育と呼びます。
中学生あるいは小学生を指導するその先には、当然大学受験というものがあります。
その大学受験を見越した形で、今、目の前の中学生や小学生たちにどのように指導していくのか、どのような情報提供をしていくのか、それがリセ教育の根幹にあります。
リセ教育とは、3つの条件で形成されます。
- 子どもたちと長期間にわたり接することが可能なポジションにある人。
- 幼い段階から子どもたちの資質を見極めることができる視点を持つ人。
- 大学受験のプロセスを理解し、適切なガイダンスを提供できる知識を持つ人。
この3点が揃えば、リセ教育というのは完成します。
これらの要素を兼ね備えているのは、私と自負しており、リセ教育を通じて、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことを使命としています。
なぜ、大学受験を視野に入れた幼児・小学生・中学生指導をしていくのか
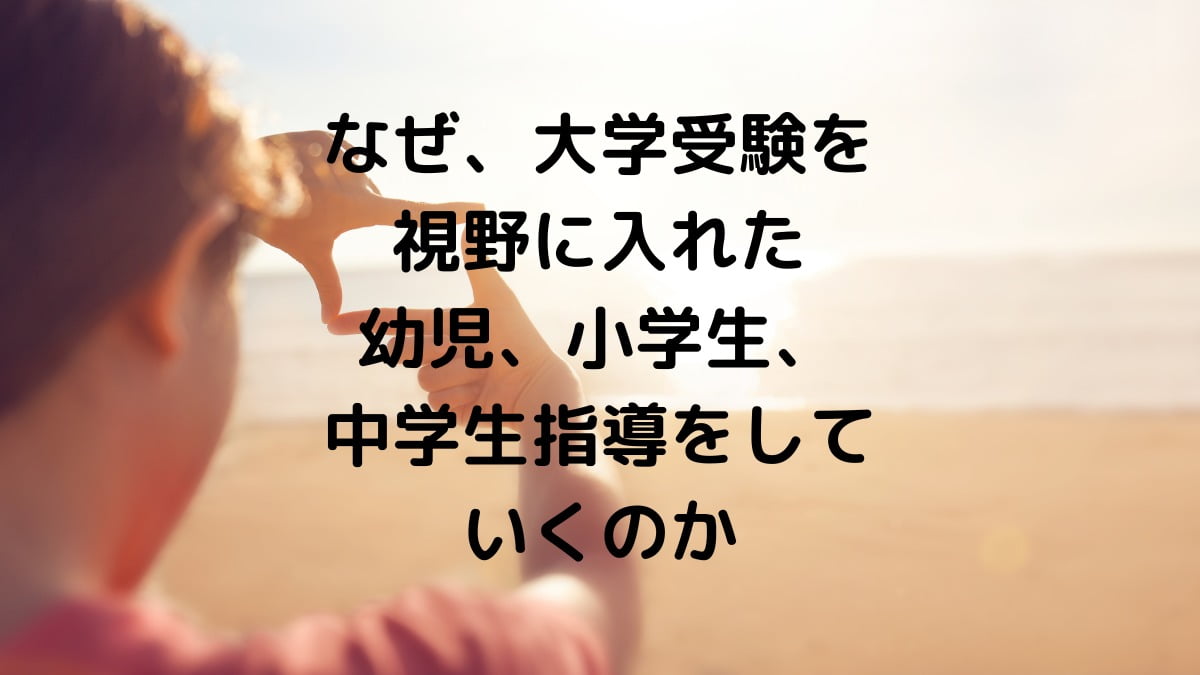
長いレンジで子どもたちの学習を見てあげられる立場にあるのは、塾です。
長いレンジで子どもたちを見ることができるという塾の強みは、何でしょう。
まず「子どもたちの資質を早い段階で見抜いて育ててあげる」ことができるということです。
例えば、九州大学経済学部経済工学科の後期試験では、共通テストは280点、小論文は300点の合計580点です。
つまり、二次試験は小論文しかありません。
色んなお子さんを指導していると、中にはこういう子たちもいます。
頭の回転が早い、あ、この子は賢いな、でも、コツコツ真面目に勉強する性格ではないので、なかなか点数に反映できない、でも試験前にちょっとやっただけで点数は一応とれる、いわゆる賢い子です。
もちろん指導の一つとしては、その子がコツコツと学習を進めていくということに育て上げるというのは確かにあるのですが、必ずしもそればかりが成功するわけではありません。
そうした場合に、例えば、作文を見てあげるわけですね。
小学校段階から作文、中学校も作文、国語の時間にそういう時間を作ります。
高校生になると、小論文対策があります。
一人一人、添削をして、鍛えてあげる。
結局小学校からだと9年間位、やるわけです。
もちろんその間に学力形成をするのですが、例えば大学受験の段階になったときに、「共通テストはとりあえず1点でも多く取っておいて、でもね、君、ここがあるよ」ということで九大をぽんと出してあげるんですね。
共通テスト280に対して小論文300ですから、9年間鍛えてきた小論文対策、それをここで活かしてあげるわけです。
それは、例えば高3になって、小論文対策講座ということで1年間勉強するのとは、質が全然違いますよね。
それが出来るのは、小学校時代にその子を見てて、尚且つ大学受験の知識を持ってて、具体的に日々の学習を進めてあげることができる立場の人間だけなのです。
それが塾の人間なんです。
超大手はそれは難しいでしょう。
(実際に、2023年に九州大学経済学部経済工学科の後期試験をトップで合格した生徒がいます。)
やはりうちのような塾では、塾長がその子を見てあげられる立場にあるわけですから、それを十二分に生かすというのが、リセ教育ということになります。
高校受験がファイナルイベントになっている塾さん、もちろんボリュームゾーンが中学生ならば、そうならざるを得ないのだと思いますが、ファイナルイベントが高校受験となると、当然そこで終わってしまうわけですから、学習指導の広がりというのも、当然そこでストップです。
でも、更に高校部があって、大学受験まで教えて、更にリセ教育の骨格を持っているということになると、おのずと中学生に対しても、小学生に対しても、更には幼児に対しても学習指導の観点というのが他の塾とは違ってきます。
これがうちの塾の強みだと思っています。
では、なぜ、大学受験を視野に入れた学習をしているのか。
大学受験に向けて、小学生、中学生にしていることなんですけれども、例えば、このHPの「塾案内」の「難関校に合格するために」というページで岡山朝日高校独自入試国語の問題に対して、東京大学の二次の英語の問題が入っています。
朝日高校受験専門と謳っていて恐縮ですが、その中で、「最終目標は、朝日高校ではない」と書いています。
まだお会いしたこともない、相手がどんな人かわからない人に、しかも「朝日高校受験専門って言っているから、我が子を朝日高校に入れてくれる人なんじゃないか、なんか凄い裏技でも使って、朝日高校に入るノウハウを教えてくれるんじゃないか」そういう思いでHPを見て下さる親御さんに対して、「朝日高校が目標じゃない」と書くと、ちょっとぎょっとされるかもしれません。
あまり書きすぎて誤解を与えてもいけませんので、過激な事はここでは控えているんですが、「私たちは、大学受験に向けての土台作りをやっているんですよ」というメッセージをこの中に込めています。
高校受験の更に先の大学受験を視野に入れた中学生指導
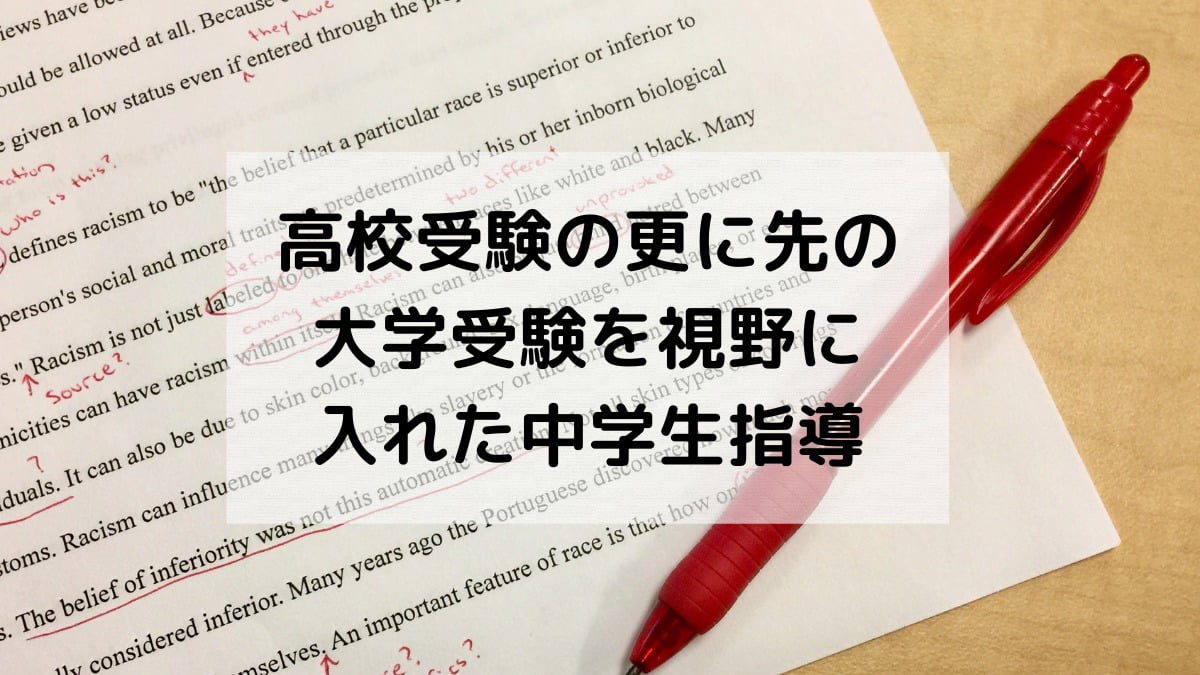
サンライズでは、大学受験を視野に入れて、幼児~中学生の間に土台作りをしています。
では、具体的にどのようにして土台作りをしているのか。
以下は、高校の文法書の一部です。
9 ▷副詞節中での注意すべき時制◁
64) I’ll talk with my husband when he comes back. (夫が帰ってきたら相談してみます。)
65) I’ll lend you another book if you have read that one. (あなたがそれを読んでしまったら、別の本を貸してあげます。)
➊ 未来時制→現在時制 (例文64)
When~「(今後)~の時に」, if~「(今後)もし~ならば」という時や条件を表す副詞節の中では、未来を表す内容は現在時制で表す。
The game will start again when it stops raining. (雨が止んだ時点でその試合は再開されます。)
↑(×)it will stop raining
The game will be put off if it rains tomorrow. (もし雨が降ればその試合は延期されます。)
↑(×)it will rain
ただし、When~が「いつ~なのか」、if~が「~かどうか」という意味の名詞節で用いられる場合は、未来の内容は未来時制で示すことに注意。
I don’t know when the next train will arrive. [名詞節]
名詞節(knowの目的語)
(私は次の列車がいつ到着するのか知らない。)「いつ~するのか」の意味ならば名詞節
I’ll ask him if he will help us. [名詞節]
名詞節(askの目的語)
(私は彼に彼が私たちの手伝いをしてくれるかどうか聞いてみます。)「~かどうか」の意味ならば名詞節
高校の文法書の一部より
when S’+V’のかたまりは、中2で学習しますが、この時、「S’がV’する時」という訳し方ができれば、中2の段階では何の問題もありませんが、このことが高1(新課程で中3から登場)で急にバージョンアップして、上記の事項を学びます。
これを中2の段階でこのまま教えておくということではなく、「when S’+V’のかたまりは何をしている?」「副詞の役割は何?」といった基本事項を押さえているか否かが、高校になって成績が伸びるか否かに関与しています。
中学生の学習指導はどちらであっても大差ないように思えますが、本来は次の高校というステップ、更に大学受験というステップをも視野に入れて学習指導を考えねばなりません。
高校受験が目的ならば、サンライズでなくとも良いでしょう。
しかし、高校受験を通過点とし、大学受験を目的とするならば、サンライズでなければなりません。
構造を学んでいくことで、英語の勉強の仕方は、中学生段階から高校レベルのものを与えないとどうなるのか。
「熟語を覚えました」
「単語を覚えました」
「フレーズとして頭の中に入っています」
だから、中間・期末のテストは解けるけれど、その先では全然役に立たないという子がたくさんいます。
それが、中学生の段階から修正できるのは、当塾じゃないですか。
私がやらないと、誰も修正してくれません。
必ず、上の学年、更にその上の学年の内容を反映させて説明することに重点を置いています。
実際、中2の塾生のノートを見ると、先ほどの文法に関連したところ「接続詞」のところで、「※ifの後は未来形にしない」と書いています。
英語では、中学校で習う単語や文法に限らず、関連があるものは先取り指導しています。
理屈っぽい説明も沢山あります。
早い段階から大学入試を意識するアンテナを立てる

先程は、高校の英語文法を中学英語に落とし込むことで、先の大学受験の土台作りをしているというお話でしたが、社会についてはどうでしょう。
以下は一橋大学の日本史論述問題です。
次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。(400字以内)
国家の仕組みの中で法制度が重要なことはいうまでもない。日本においては、7~8世紀に制定された「律令」を通じて、本格的な法治体制がとられることとなった。しかし、(1)「律令」には社会の実情と合致していない面もあり、その原則は徐々に崩壊し、10世紀には大きく変質した。12世紀に成立した武家政権である鎌倉幕府も、(2)基本法典として「御成敗式目」を制定したが、その性格は「律令」とは大きく異なっていた。応仁の乱以降地方分権化が進むと、地域政権である戦国大名は、それぞれ(3)「分国法」を制定して支配の規範とした。その後新たな統一国家を完成させた徳川家康は、大阪の陣後直ちに(4)「禁中並公家諸法度」・「武家諸法度」など身分ごとに基本法を制定した。
問1 下線部(1)に関し、「律令」によって規定された土地・人民支配制度の特徴と、その崩壊の方向および変質の内容を具体的に説明しなさい。
問2 下線部(2)に関し、「御成敗式目」の特徴を、「律令」と対比させて説明しなさい。
問3 下線部(3)に関し、「分国法」に取り入れられている、社会の変化に対応した新しい紛争処理方式の内容を説明しなさい。
問4 下線部(4)に関し、「禁中並公家諸法度」を制定した目的、および、この法度で対象となった身分集団に与えられている役割について説明しなさい。
見た目がいかついですね。
注目すべきは問2です。
御成敗式目は鎌倉、律令は奈良です。
教科書の太字をそのまま覚えてどうだ、という一対一対応の勉強では、こんな問題は解けません。
しかし、御成敗式目にせよ、律令にせよ、知識としては小学校・中学校で習いますよね。
このレベルに達する必要があるので、社会は考えてやる教科なのです。
社会は、一番考える必要がない科目だと思われている方が多いです。
「要は、一対一対応で覚える、覚えれば点数が取れる、だから考える必要がないでしょ」
でも違うんです。
それだけでは、入試に対応できません。
だから、うちは「考える社会」を教えています。
お子さんのノートを見てみて下さい。
「考える社会」のノートになっていますか?
それはなぜですか?
字がきれい。
見やすい。
もちろんそれに越したことはありませんが、要は社会をどのように捉えて、学習してきているかが、ノートを見るだけでわかるのです。
一般的な勉強では、教科書に書かれたようなことを、いわゆる一対一対応で並べたものが多いです。
サンライズの授業では、
「なぜそうなるのか?」
「どういう背景で現在の社会になったのか」
「問題点は何なのか?」
について、教えています。
最近は、高校入試や定期考査でも考えさせる問題は増えてきていますから、今の受験では一対一対応の勉強が通用しなくなってきています。
今の中1なんかは、新課程の学年ですが、既に英語の点数に表れてきています。
平均が30~40点位に対して、うちの塾生はというと70~80点。
ほとんど倍です。
一対一対応で点数を取ってきた人にとっては、戸惑うでしょう。
もちろん、全員がきちんと勉強できている訳ではないので、繰り返し繰り返し根気強くやっていく必要があります。
ついでに他の科目についても、授業における具体的な取り組みを少しお話しますと、国語では、小4から、主に中学入試から大学入試の問題までを取り扱っています。
算数では、中学校とかぶる内容は教えますし、数学では、確率の問題などで、高校で習うやり方を使えば早いので、それを教えたりもします。
もちろん、先取り授業をしているよ、ということではありません。
こういった環境、習慣作りをしていくことは、早い段階から大学入試を意識するアンテナを立てるんだよということのメッセージです。
基本的に、高校部があって、最終的に大学受験を目指しているわけなのですから、小・中・高がきちんと連携している、リンクしている状態を作らないと、あんまり意味がないじゃないですか。
だから、高校部があるということは、きちんと小・中学部の中に落とし込んでいくということ、全体としては同じベクトルを持っているということを御理解下さい。
大学入試の現状から、子どもたちに対して何を学ばせるのか
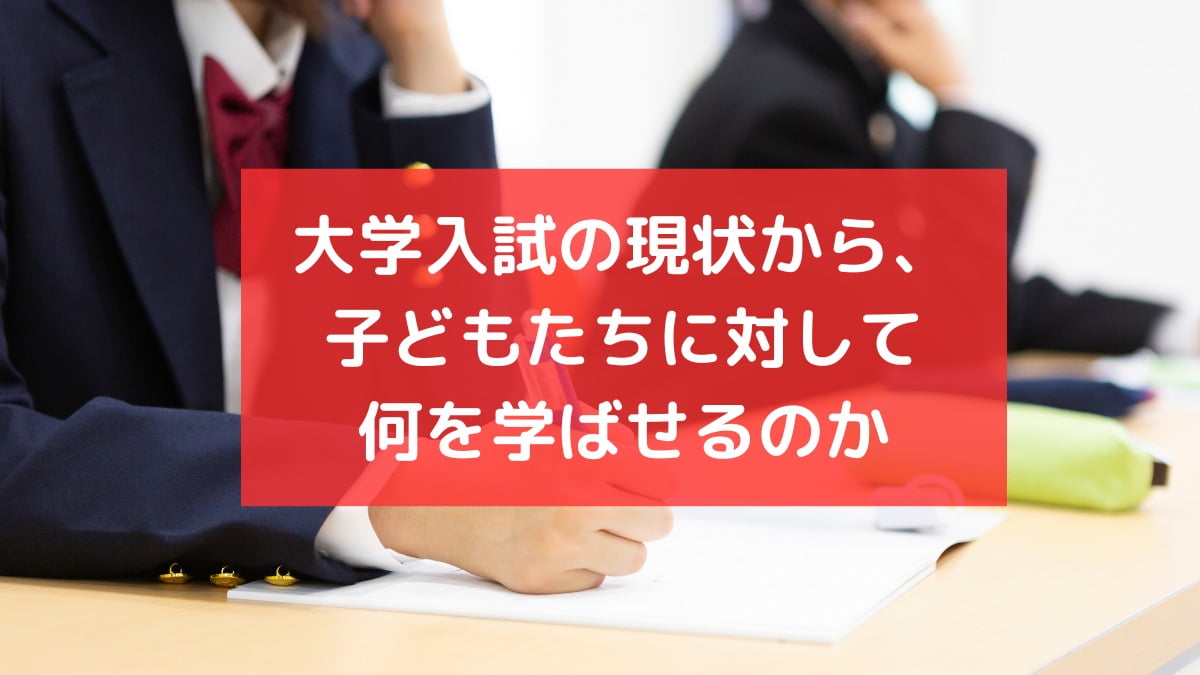
ほとんどの親御さんは、高校生になった場合、高校生の学習は高校任せです。
岡山朝日高校の進学状況を見てみてください。
岡山朝日高校の公式HPから見ることができます。
学年360名です。(令和7年に高3が320名になります。)
岡山県下トップ校ですよ。
そのうち、現役生の国公立大学合格は令和2年が170人、令和3年が177人、令和4年が199人です。
少しずつ増えてきていますが、その割合は、令和2年が約47%、令和3年が約49%、令和4年が約55%、ようやく5割を超えてきたところです。
10年前は、117人で約37%、4割を切っていました。
それだけしか国公立大学に進学していない。
どうですか?多いですか?
岡山トップ校ですよ。
トップ校でこんな程度?と思いますよね。
イメージとしては、どこも一緒だと思うのですが、超進学校やトップ校に行けば、東大や京大や阪大やといった旧帝大系といったところにちょっと頑張れば行けるよ、というようなイメージを持っている人が多いと思うのですが、全然中身は違います。
これは岡山だけの話じゃなくて、他も一緒だと思うんです。
それは、高校が悪いというのではなくて、現実を見て欲しいのです。
トップ校でもこんなもんなんです。
ですから、準備をしなければならないのです。
大学受験を視野に入れた指導であるということから、高校受験のハードルが意識的にぐっと下がります。
高校受験をファイナルイベントにしてしまうと、そこのハードルが100%になるんです。
でも、その先にある大学受験を視野に入れた学習計画をすると、自然に高校受験のハードルがぐっと下がってしまう。
「行って当然でしょ」というような形になっていく。
そのことによって中学生の意識は随分変わるのです。
以下は、京都大学 前期 経済学部の問題です。
Aは、日本の社会と文化、つまりは日本人の意識の構造の特徴として、集団の絶対化や空間に対する部分尊重主義、歴史的時間に対する現在主義等があげられる、と述べる。Bは、時間的空間的に離れたものに我々が付与する重要度は、遠く離れるにつれ、一般的には低下する。しかし、世界的な通信と航空輸送および科学の発達で、時間的空間的視野が著しく拡大した。それをふまえて、我々の行為の本当の結果は次回以降のために初期条件を設定することで、この世を次世代の人に残す時、彼らにとって良い初期条件とは何かを問う。
設問3
Aが示している日本文化の「時間、空間をめぐる(部分と全体の関係)についての世界観」をめぐる特徴は、現在の国際社会が抱える問題(例えば、国家・宗教間の対立の問題、環境問題、経済格差の問題など)の解決に日本が取り組む上で、どのような長所と短所をもっているのか、Bが論じている社会的なシステムの設計の在り方と対比させながら、議論せよ。議論に際しては、現在の国際社会が抱える重要な問題をひとつ取り上げ、できるだけ具体的に論じよ。
京都大学の前期の経済学部の小論文より
「全然そんなのまだまだ先でしょ」とお思いでしょう。
でも、中1なら後6年でこれが解けるようにならないといけないんです。
難しいですよ。
これが現実なんです。
他の大学も同じです。
そんなに簡単ではない。
だけれども、後6年でそれをせねばならない。
つまり、漢字がどうしたとか、英単語が覚えられませんとか、そういう次元の話をしているのではないのです。
カタカナ語にアンテナが張れるか
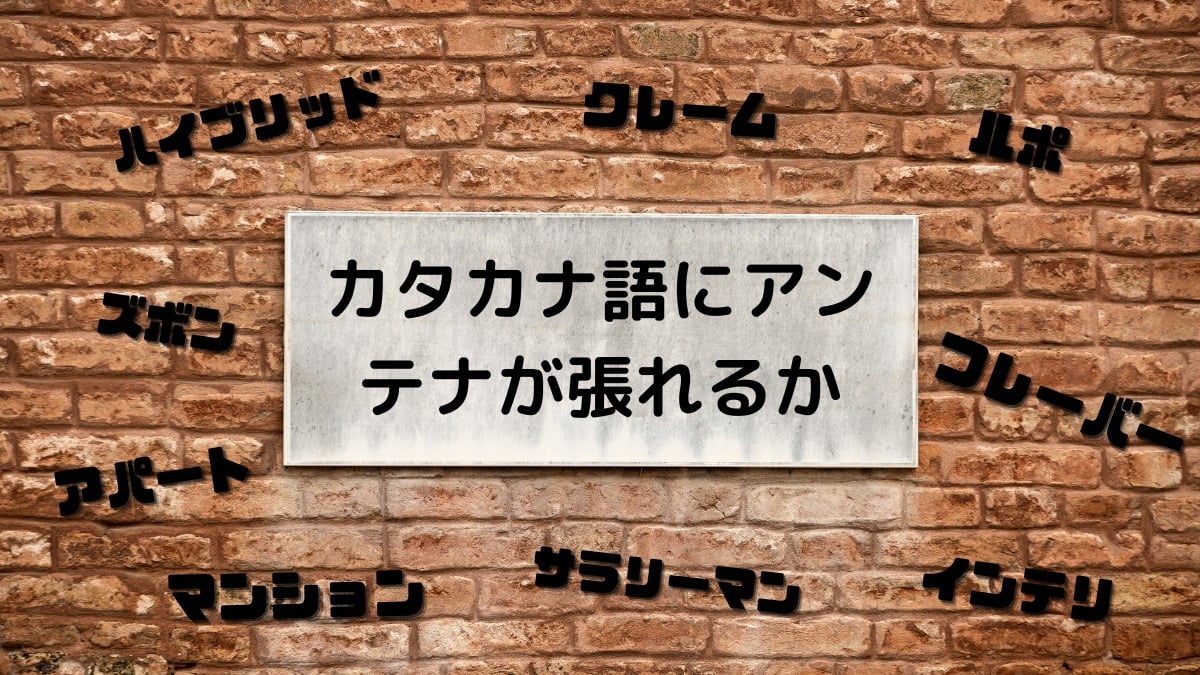
以下は、岡山大学前期試験の英語の問題です。
3 (前略)
The human brain is built in a way that ensures our memories are faulty. We are a self-concerned interpreter of all incoming information. At any given moment, we may note only one aspect of a current flow of information, depending on our view of ourselves, our attention, and our emotional state in a specific situation. Later, we may note still other aspects of a similar flow of information. Then , when an attempt to recall the second moment is confused with the memory of the original moment, our brain starts to create a tale to take in different aspects of both the original situation and the second moment. We suddenly confuse the episodes, as we begin to put the two sets of events into some kind of ④memory hybrid. Alas, accurate memories are an idea, not a reality of the human condition.
(4)下線部④の内容を解答欄(3行)に収まる程度の日本語で説明しなさい。
4 次の例文を読んで、下線部(1)、(2)、(3)を英語にしなさい。
こうして毎日新聞福岡総局学芸課・福岡賢正の実験が始まった。
(中略)
(2)3ヶ月目、張り切り過ぎて具合が悪くなった。家族で話し合って、「ねばならない」という窮屈な考えを捨て、「してみよう」と考えることにした。
(同記者の体験は毎日新聞に連載され、その後、本として出版されている。)
「(3)振り返ってみると、一年にわたるこのルポで私がやってきたのは、生きるということの実感を取り戻す作業だったような気がする」と福岡記者は書いている。
岡山大学 前期試験 英語
英語は、小学生から指導します。
日常の中に転がっているカタカナ英単語、いわゆる外来語ですね。
小学・中学段階では、どれだけそれにアンテナが張れるか、ということです。
注目すべきは、問4です。
memory hybridのハイブリッドって何?と中学生に聞いてみると、一番多かった答えは、「プリウス」だそうです。
まあそうですよね。
一対一対応になっていますけど。
ちょっと勉強の出来る子は、「エコ」と答えます。
なるほど。
もう一段、思考が先に行きますよね。
でも、もちろん2つとも違いますよね。
hybridとは「複合」ですね。
いわゆる一対一対応で知識の理解をしている子は、日常の勉強の中でふと耳にしたカタカナ英単語を一つ崩してあげるんですね。
ハイブリッドが複合だとわかったら、その英文のhybridという単語の右斜め上にbothってありますよね。
bothというのは「両方」ということですよね。
つまり、そこに視点を移して、そこから先を訳せばいいじゃんっていうところができるかできないか、というのは、非常に大きな問題なのです。
入試問題を頭から訳していたらできませんから。
その下の問題を見て下さい。
(3)の問題です。
「ルポ」
ルポって何ですか?
ルポルタージュというフランス語の略ですけども、英語で考えても、答えに行きつくわけがないですよね。
リポートに直せるかどうか。
リポートなんて、日常の中に転がっているじゃないですか。
このように、問題集をカリカリ解いていてもたどり着けないものについては、誰もが自然と身につけるわけではありません。
だから早い段階からアンテナを張る=意識させる、目を向けさせる、注意をひきつけることによって、知的好奇心を向上させていくのです。
本質的な学習は、実は非常に地味である
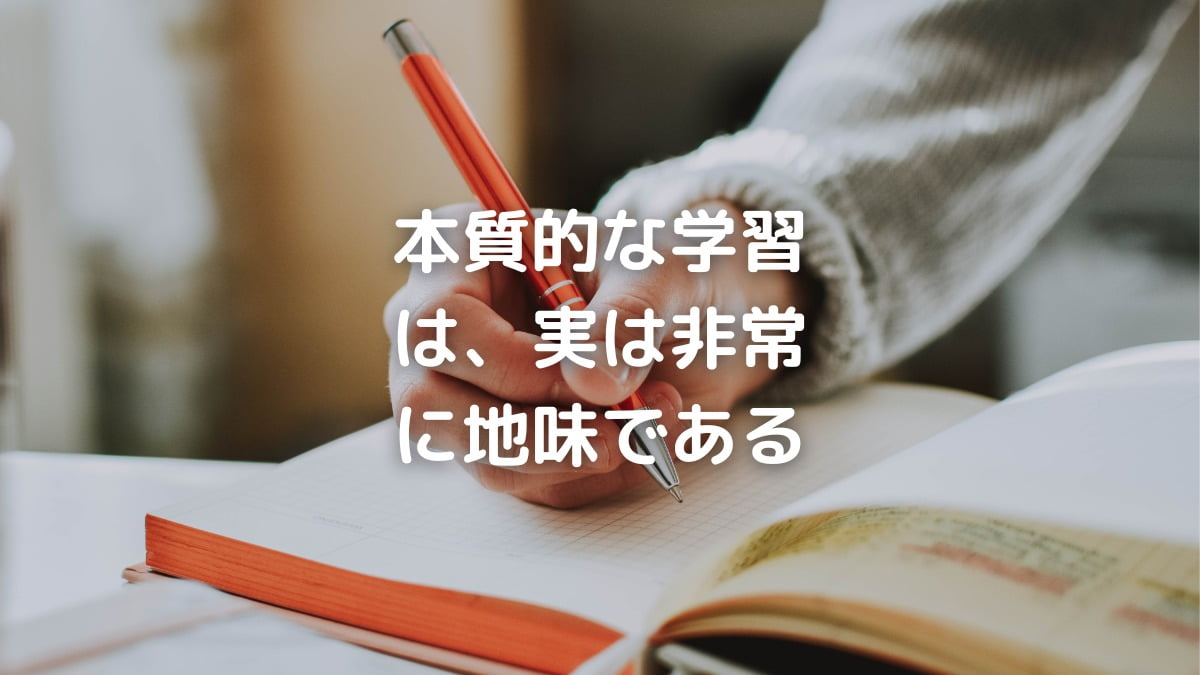
よくある例として、「アンテナを張るようにさせる」ために、「勉強のために」とか「点数につながるからやろう」などと「勉強しようぜ」という空気を作ろうとするとうまくいきません。
以下は有名な文ですので、御存じの方もいらっしゃるかと思います。
Too much travel, too much variety of impressions are not good for the young, and cause them as they as they grow up to become incapable of enduring fruitful monotony.
アメリカの心理学者Bertrand Russell(バートランド・ラッセル)の談話から
最後に「fruitful monotony」という言葉があります。
これは、学習に対するアメリカの心理学者の論文なんですが、基本的には、「刺激を与えすぎると無感覚になる」言いたいことは、そういうことです。
それを現実、我々の日々接する問題に言い換えると、「勉強、勉強、勉強」という刺激を与え続ける、「点を取れ、点を取れ、点を取れ」「中間点を取れ、期末点を取れ」これも刺激です。
これを与え続けると、当然無感覚になる。
でも、本質的な学習というのは、ものすごく地味なんですよ。
イベントがあって、一瞬盛り上がって、わあ~となって勉強する、で、しばらく経って、また勉強しない。
こういう繰り返しは、中学校の高校入試システムに対してはまだ何となく対応できるのですが、大学受験ではもう歯が立ちません。
ですから中学生のうちにそれを修正しておかないと、高校生になって大学受験に耐えうる学力形成をすることができる子どもにならないのです。
高校生の勉強は、非常に地味な作業です。
我慢のいる作業です。
それをさせないと高校生の学力は溜まりません。
で、その習慣を身につけさせるのは、小学生、中学生のうちです。
中間、期末テストの前に、イベント的にバーっと集中してやるというのは、たくさんの塾さんがやっています。
そのこと自体が悪いわけではないのです。
そのこと自体を否定している訳ではないのですが、そのことだけで終わってしまっている方がほとんどなので、それはちょっと問題が出るよ、という風には思っています。
プラスアルファのことを継ぎ足しさえすれば、修正できるのになあと思っていますが、結局、その刺激物をあまり過剰に与えないということ、それが大学受験を突破できるレベルに育て上げる一つのキーワードではあると思います。
ちなみに上記のラッセルの話の前後の文も非常に興味深いです。
A child develops best when, like a young plant, he is left undisturbed in the same soil.
訳:子どもというものは、若い植物と同じで、同じ土壌でいじくられないで放っておかれるとき、もっともよく成長します。
I do not mean that monotony has any merits of its own; I mean only that certain good things are not possible except where there is a certain degree of monotony.
訳:単調であることがそれ自体良いと言っているのではなく、ただある種の良きものはある程度の単調さがあるところ以外では育たない、と言いたいのです。
器理論

私が、小学生・中学生の育成の根本においているのは、「器理論」というものです。
器というのは入れ物ということですが、中学までの段階は器を大きくするのに力を注ぎます。
器を大きくしておくことにおいて何ができるかというと、高校生になって自分で考えて勉強できるようになるということです。
これができるようになると、学校で1年間でやることを、早い子は2周くらいできますので、当然合格の可能性が以前にも増して上がってくる子がいます。
例えば、高1の秋の段階で高2にもう入っていると。
共通テストの準備は高2の中ごろからしていると。
そういう状況は実は作り出せるんですね。
基本的に高校生は時間がフリーですから、うちの塾ではよく「塾長、今週の土曜日は朝から晩までいくよ」とかですね。
すると数学だったら、「数列全部をこの週末で」、そういうことができるわけですね。
それが週1で講師が教えるものとやっぱり違うので、学習の効果というのは大変大きいものがあります。
ただ、学習習慣が身についている子でないと、どんなにそのシステムを用意してもうまく機能しないんですよ。
そのために、器を大きくしてあげるのです。
具体的にはどういうことかというと、例えば、中学校の定期考査で5教科で480点とった子、仮にAさんとしましょう。
また、Bさんは420点とったとします。
ただ、器の部分を見ると、Aさんはいっぱいいっぱい、Bさんは結構ある。
で、Bさんのような子を作らないと、大学受験に耐えられるような高校生にはなかなかなれないですよ。
もう、高校受験でいっぱいいっぱいなんです。
要はデジタル式に勉強しているのです。
この子は点数が取れるからと、何回も反復させて、うるさく言って、という風にして。
本人もそれで良いと思っている。
中学まであるいは高校受験の合格日まで、ご家庭も子どもも大変満足なさっています。
でも、高校に入って、夏休み過ぎたぐらいから、ちょっと、え?という感じになってくる。
アップアップして。
それは、器が小さいからです。
だから、その器の部分を大きくしてあげるのです。
具体的にはどういうことなのかというと、先ほどから何回も出てますが、物事をデジタル式に一対一対応で覚えたら終わりというようなことで点を取らせないために、大きくわけて2つの力を育成します。
- 頭の中を整理する。そのやり方を徹底的に教えてやる。
- 物事を分析する力をつける
これらができるということは結局応用できるということです。
一般的にはそれを応用力といっていいのかもしれませんが、そういう能力が身につくということです。
この2つを育成してやると、学んだ情報を有機的に結び付けるような思考が身に付きます。
定期考査脳にしない
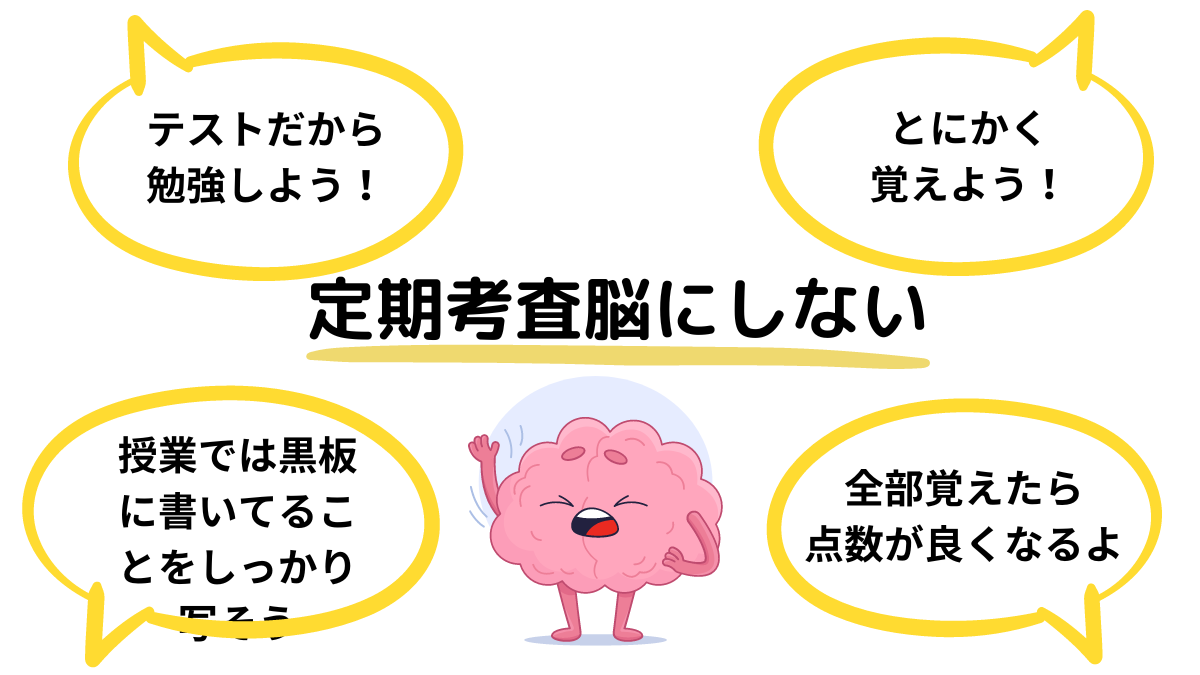
器を大きくするには、2つの力を育成するということをお話ししました。
そのことについて、具体的なお話をします。
岡山朝日高校の入試は、自校作成問題、つまり独自の問題なわけですが、それが簡単だという人もいます。
実は結構難しいんですけどね。
例えば、令和4年度の数学の問題。
問3の問題について。
3桁の自然数N がある。 Nが3の倍数であるとき, N の各位の数の和も3の倍数であることを証明しなさい。
この問題、正答率は7%です。
岡山朝日高校を受験するような子でもほとんどの子が解けない。
でも、このことは小学校や中学校で学んだはずなんです。
問題は解いたことがない、見たことがないとしても、「自然数」「倍数」や「証明」「文字式」を知っている。
だから頭の中を整理して、分析する力があれば、このレベルの問題が解けないということにはならない。
でも、有機的に情報を結び付けることができないんです。
育成していく上で邪魔になるものがあるのです。
私は「定期考査脳」と呼んでいます。
定期考査の点を取るために勉強しているという風に思っているようなことを長くしていると、本当に脳がそういう風になって、先ほどのような分析力とかいうのが身につかなくなります。
中学のレベルだったらテスト前に長時間勉強して、英語だったら教科書の本文を何回も書いていったら、点が取れますからね。
すると、なかなか大学受験を突破できるようなレベルの子どもにはなれないのです。
中学の時はすごく点がいいですよ。
でも応用が利かない。
私はそういうタイプの子を定期考査脳といって、大変危険視しています。
「点を取るためだけにするな」ということを何かの形で教えてあげないと、親も子もこの点数に満足しているのです。
おそらく高校受験も突破できるでしょう。
トップ校にも行くでしょう。
学校の成績もいいのですから。
でも、トップ高校に行って、すごい挫折を味わって、心が凹んで何もしなくなる。
もう沢山そういう高校生を見てきました。
そういう子を作ってはいけないということです。
で、中学の時にそのことを注意してあげる。
そしてここでもう一つ、とても大切なことがあります。
高校生の勉強をする時には、どうしても中学生の段階で養っておかなければいけない力ですが、学校の授業を受ける時に、ものを聞く力が養われていないと、講義形式で力をつけることはできません。
子どもたちが学校で受けている授業は、一斉形式ですよね。
ですから、一斉授業で聞く力がなかったら、塾だけでなく、学校の授業でも力が身に付きません。
今は個別指導形式の塾というのが多いです。
個別というのは、一対一なんです。
一斉ではないんです。
それが高校になって、よく知っている人ではなくなって、よく知らない人がやってて、内容も難しくて、「え~何だかよくわからない」と思うのは当然なんです。
ですから、高校でうまく授業を理解するためには、小学校や中学校から聞く力を養ってあげないと、なかなか高校からの授業についていくのは難しいと思います。
だから、子どもたちにはこう言っています。
大学生になったら、大学の先生は黒板をほとんど書きません。
ばーっとしゃべって、書くのは題程度で、大学生は皆肝心な事をノートに書いています。
で、それができる人が大学生になっている。
じゃあ、高校はどうか。
高校はある程度書いてくれる。
でも、先生はこう考えて、こう考えて、こうなったから、だからという説明なんかはどこにもないですよ。
例えば、物理。
式書いて答え、それだけです。
でも答え書いてもしょうがないじゃん。
「こう考えて、こう考えて、こうなったから」というところを聞かないとダメなんでしょ?
それを書くんでしょ。
あなたたちのノートは答えだけじゃん。
そんなノート役に立つの?と振って、じゃあこれからばーっと言うから、どれだけ書けるかやってごらん。
というな授業もしています。
それから、息継ぎも大切にしています。
黒板を写すだけの子は、息継ぎが多い。
わかりますか?
顔を黒板とノート交互に往復させて、まるで水泳の息継ぎみたいな状態です。
一方、必要なところだけ書いている子は、聞く力があります。
息継ぎが多い子は話をほとんど聞いていないので、理解しようとしていません。
それは何回も何回も言ってやらないといけないのです
受験勉強にも通用する勉強を
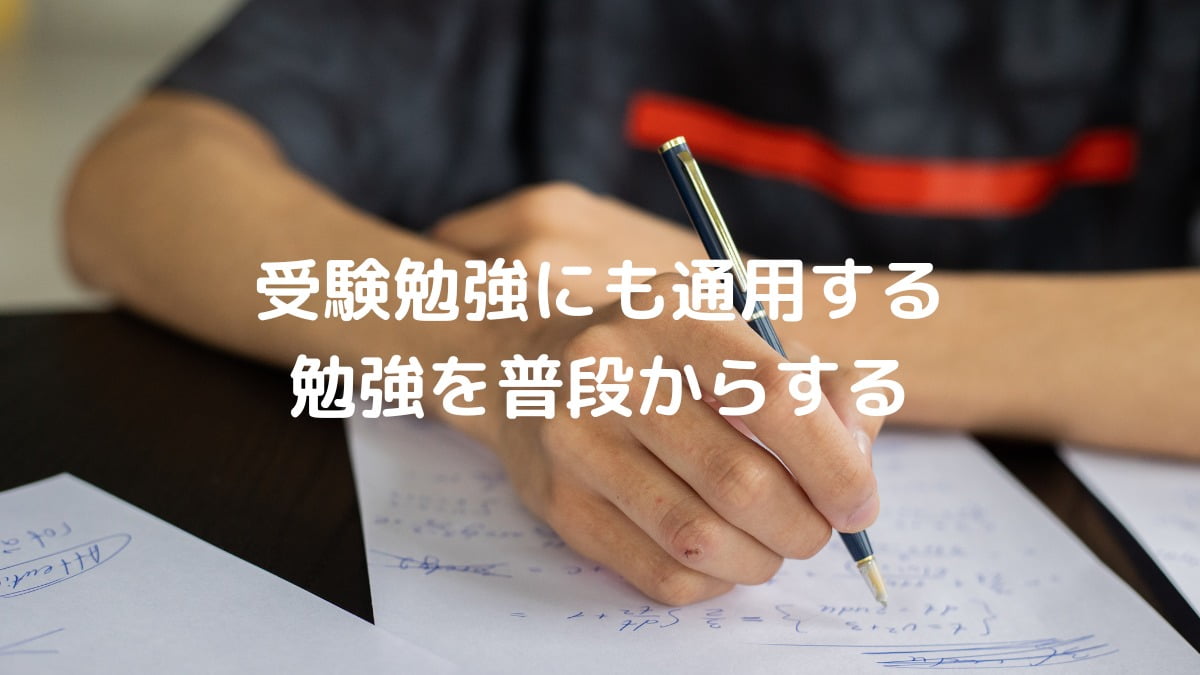
高校入試は、偏差値から大体合格率がわかりますが、大学は配点が違うため、偏差値で話ができません。
定期考査の勉強と受験勉強と何が違うか。
高校1年生の1学期古文教科書には、大体「ちごのそら寝」というのを、皆やります。
その中に出てくる「わろかりなん」の「なん」。
古文に「ん」はないです。
「ん」=「む」だということを知らない時期です。
1学期ですから。
なのに、定期考査で出るんですよ。
長文読解ですよね。
で、訳をみんな丸覚えしていったら満点です。
「わろかりなん」=「きっとよくないでしょう」覚えとけよって言われて。
「わろかり」は形容詞で、「な」は完了の「ぬ」で「ん」は推量の「む」と覚えとけと言われて、覚えるわけですよね。
で、○をとる。
それで100点を取ったとしても共通テストの問題ではどうでしょう。
「なほひたぶるにいぶせくてやみなむ」の問題を引き出して、「なむ」はどういう意味かがわかっているかを問う問題になっています。
共通テストが教科書レベルだから、だから学校の定期考査をすればよいという問題ではありません。
アプローチが違います。
うちの塾では、いわゆる受験勉強というのは、「なん」というのは4つあって、区別できる日が来ないと共通テストは解けないんですよ、と教えている。
それが受験勉強です。
ですから高校生になれば、1年生の時から共通テストに対して準備をしていくような、そんなトレーニングになっています。
これまで指導してきて、よくあるパターンなのですが、「中学までは英語ができた。」「英検2級もとっていた」、それが高校生になって、いきなり英語が分からないとか、英語の点が悪いとか、特に実力考査に多いですね。
そういう子どもたちは英文を覚えて、訳を覚えて、というのをやって、点を取ってきています。
しかも英検も65%○があってたら、次に行けるんですね。
100%のものではありません。
それだけが全てだと思って、英語が得意だと思っていると、勘違いが生じて、
「塾長、何かこの参考書だと、うちの子英語がわからないって言うんです」
「塾長、なんだか教科書と違うことやっているから、英語がわからないって言うんです」
と言われます。
それは、そうではなくて、中学までの英語のアプローチと高校の英語、あるいは大学受験の英語のアプローチが勉強の仕方が違うからです。
勉強が苦手な子の話をしているのではないですよ。
中学校でのいわゆる上位層でも起こりうることなんです。
中位層の子は、小学校から中学校に上がった時にも英語のアプローチの違いに戸惑います。
英検というのは、正式には、「実用英語検定」といいます。
「実用」です。
就職試験のTOEICには繋がると思います。
しかし、大学受験用ではありません。
そのことは御理解でしょうか。
高校に入ると英語は理屈っぽくなってきます。
その理屈っぽいことについていけない。
だから英語がわからないのに、それを責任転嫁しないようにしなければいけません。
例えば大阪大学の二次試験の英語の問題。
英作で流行りの自由英作です。
うそをつくことは悪いことでしょうか?あなたの意見を英語で述べなさい。
一橋の場合は、
人生において、ユーモアは最も大切なものの一つであるということについて、あなたの意見を120~150字の英語で述べなさい。
東大は2011年から自由英作に参戦してきました。
他人の痛みを理解できるのは、不可能である。ということについて50~60語の英語で記せ。
これが、大学受験の二次のレベルです。
まず、これに対して意見が持てない人は、英語以前の問題です。
意見がないと書けません。
そして、意見を頭に浮かべたものを英語に直す。
だから、いわゆる「実用」しゃべれる英語ではありません。
読み書き英語です。
だから、そのことをよく理解して頂きたいのです。
以前お話した中でも、高校の文法書の話がありましたが、「時、条件を表す副詞節の中では、未来形は現在形で代用する」なんて、めちゃくちゃ理屈っぽい説明ですよね。
それが大学受験の英語なんです。
今までとちょっと感じが違うということを子どもも理解しないと、何を使ってもそれがよくないんだと勘違いされるんですね。
例文を覚える訳にはいかないですね。
自分の意見を英語に直すんですから。
そういうことではないです。
根本的に力を持たないと、無理なんです。
だから反対に、定期考査のものを丸暗記して点をとったって、このレベルにはならないですよね。
だからうちの塾では、このレベルが解けるようになるために準備を続けていく、そういう風になっています。
宿題のこともあります。
予習、復習、宿題。
中学校、高校、学校によっては、あふれるほど出すところもあります。
宿題が沢山出てきて、学校のことでいっぱいいっぱいです。
だから受験に向けた勉強なんてする余裕がありません。
とかですね。
共通テストの国語は理系文系どちらも受けます。
大変レベルが高いですよ。
作業のような宿題。
宿題が出たからやる、答えをもらって、赤で適当に書いた。
そういうことを週末ごとに使っていて、現役で入試レベルの国語が解けるようになりますか。
ある程度そこは上手に考えて、時間を作って、1年生から準備をするんです。
受験勉強は、何か受験生になってちょろっとやればいいんでしょ、というようなイメージではないのです。
子どもにアンテナを向けさせることができるのは母親

岡山県立高校の入試問題より
次の文章を読んで、問いに答えなさい。
手紙が来なくなった、とつくづく思う。ここに私が手紙というのは、人がペンや筆で書いた葉書や封筒のことだが、そういうものが本当に来なくなった。毎日、相当数の郵便物が届けられるが、中に手紙があることはめったにない。
たまに全部筆で書いた葉書や葉書が来る。そういうときは生きた人間に触れたようで、二度も三度も読む。文章ばかりでなく、文字、インキの種類、便せんや封筒の選び方までその人の人柄がにおってくる気がする。
その昔、私が二十代のころは、郵便物が下宿住まいの私に来ることはめったになかったが、来た手紙はどれもそういう手紙ばかりだった。書き手はほとんど友人たちだが、彼らはその中に、ふだん顔をつきあわせるときは言えないようないろんな思いをこまごまと書いてきた。そういう手紙が来た日は、それだけで一日が明るくなった。だから、当時のそれらの手紙だけは、今も大事に保存してある。
私が手紙を大事にするのは、手紙というものは、顔つきあわせていたり電話では言えない、その書き手の奥深い思いが行間からにじみ出ているからだ。愛するなんてことばは日ごろ人は恥ずかしくて相手に言えないが、文章の中ではその思いさえことばで表せる。
それにしても、日本人はなんと手紙を書かなくなってしまったことか。用事は電話ですます。それはそれで結構だが、手紙を書かなくなったという現象には別の理由がありそうだ。
手紙を書くとき人はひとりである。相手を頭や心に思い浮かべつつその人に向かって書く。孤独の中で人とあるいは自分と会話をかわすという心の習慣が失われてしまったのかもしれぬ。
私はやはり、だれもが自分の手で手紙を書く習慣を取りもどしてもらいたい。私はその昔、便せんの上に涙がこぼれてにじんだらしい痕のある手紙をもらったこともあるが、手紙にはそういうことを含めて書く人の全部が出るのである。そんな手紙は、人が生きた最も貴重なしるしだ。人生の痕だ。私の母は手紙などめったに書かなかったが、それだけに母から鉛筆をなめながら書いたとおぼしき誤字、当て字だらけの手紙が来ると、見ただけで胸がつまった。その母も亡くなった今、私にはそれは最も貴重な母の形見である。
出典 中野孝次「生きたしるし」
一番後ろから2行目あたりをご覧ください。
これが設問になっていました。
「なぜ筆者は胸がつまったのか」という問いでした。
これを、ある塾さんで中学生に解かせたそうですが、全員同じ答えになったそうです。
岡山トップ校と言われる朝日高校を狙っているような子でも、です。
何と書いたか。
「母は認知症だったから」
本当に!?と思うでしょうが、この答えだったそうです。
「なぜその答えになったのか?」と聞いてみたそうです。
当然小説、文章ですから、証拠を探せというのが学習の方法論ですよね。
どこに証拠があるの?というと、
「えんぴつを舐めながら」
「誤字、当て字だらけ」
そう、正解なんです。
答えを導き出す鍵となる場所は、あっているんです。
あっているんですが、でも答えは「認知症」になるんです。
それは、明治は、特に女性が学校に通って読み書きをあまり習うことがなかった。
いわゆる文盲ですよね。
「文盲の方が多かった」という事実を今の子どもたちは知らないんですよね。
ではそういうところからも、全部学校で教わることですか?というと、それはちょっと違うような気がします。
つまり、日々の生活の中で、そういうところにアンテナを向けさせることができる大人は、それはお母さんじゃないですか。
お父さんではない、塾でも学校の先生でもない。
一番お子さんと接している時間が長いお母さんです。(※ お母さん以外の場合もあるでしょう。)
お母さん自身が子どもたちのアンテナを磨く役目をしなければならないんじゃないですか。
例えば文盲であるというのは、テレビドラマであるとか、映画であるとか、そういった諸々の中には必ずどこかに触れているはずなんです。
でも、アンテナが立ってないから、そのことがそのままスルーされてしまう。
そうじゃないでしょ。
子どもたちの日々のアンテナをよく立てるということが、お母さん、あなたの役目なんです。
家でちょっとそのあたりを注意して下さい。
一対一対応で覚え物を山のように覚えていかなければ知識が習得できないという、そういう状況に育ててしまうと、子どもたちの方がかわいそうじゃないですか。
文盲だという一つがあれば、答えに行きつくことができる。
それは決して机で鉛筆を持って勉強して得られる知識ではないと思うんです。
日常の中で得られる知識を磨いてあげるということが、必要ではないでしょうか。
以上。長文にも関わらず、ここまでお読みいただきありがとうございました。

