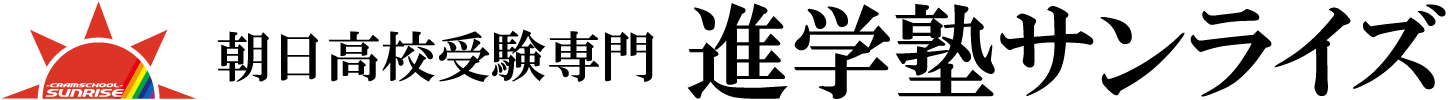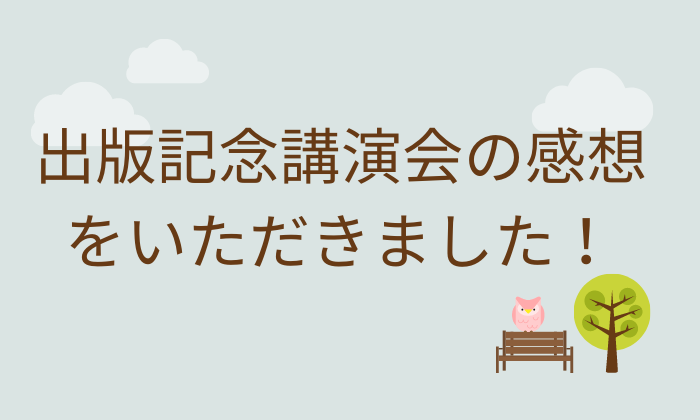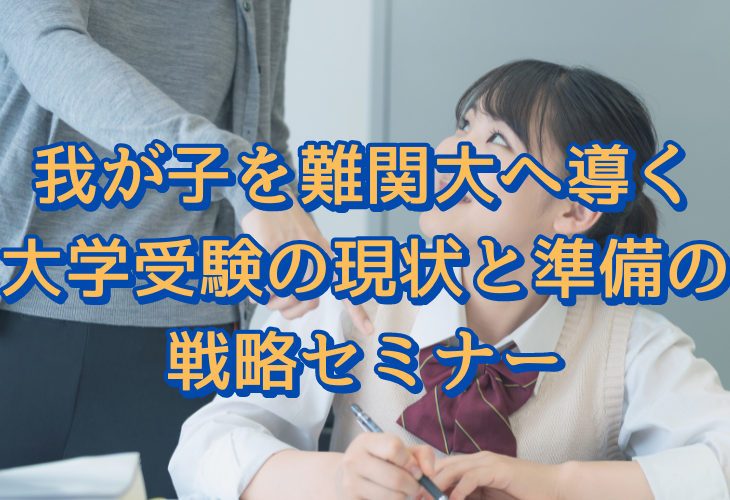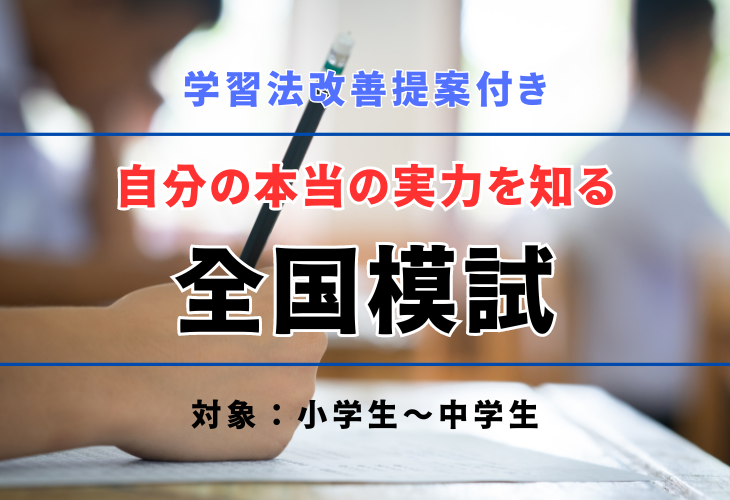KADOKAWA出版記念講演会「自学力の育て方~受験突破だけで終わらないために~」のにご参加いただいた方々から感想を頂きましたので、ご紹介させていただきます。
セミナー興味深く拝聴させて頂きました。
今日、セミナーで伺った内容をいくつか話してやりました。
聞いているのか反応がないように見えましたが、大切なことの根本はちゃんと理解していました。
勉強体力をつける努力もするそうです。
頭では分かっていても行動にうつすにはなかなか難しい年ごろなのかもしれません。
少し前を並走しながら、結果をすぐに求めずに残りの中学生活を過ごしていく努力をしてみようと思います。
用意されていた資料の多さと時間をおしてまでも伝えたい塾長の熱意を感じました。
ありがとうございました。
セミナー開催をありがとうございました。
毎回、子供への関わりを振り返る良い機会となっております。
過干渉になりがちなので、子供自身が決められるよう並走するように気をつけたいと思いました。
昔は分からない問題に直面するとすぐに親に聞いてきて、教えてしまっていました。
依存させてしまい、自分で考えないようになってしまうところでした。
自分で考える事が大切と何度も教えて頂き、子供も自分でやり抜こうと努力するようになってきています。
図鑑などその時見たら終わってしまい無駄かと思う時もありましたが、種まきですね。
たくさん書籍があり、いつもどれがよいか悩むので、具体的に紹介していただき参考になります。
低学年から種まきをたくさんしていきたいです。
小崎先生、本日は貴重なお話と時間を有難う御座いました。
大変有意義なお話しで、家族の中で話し合うきっかけになりました。
早速先程息子と3人で、スマホゲームの使用ルール、自宅学習の環境など話し合いました。
ご紹介頂きました理社の本も早速購入します。
引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。
自学力が学生の間だけではなく、社会に出た後も他人と関わり仕事をする上でどれだけ大事なのか、大変勉強になりました。
小学生の間まではずっとダイニングテーブルで勉強していた息子でしたが、中学に入りサンライズに通塾するまでの間オンラインで塾に参加していた事もあり自分の部屋で勉強する様になりました。
どこか安心した様な、でも見えない環境の中で本当にきちんと集中できているのか…少し不安でもありました。
今日先生のお話を聞いて、改めて伴走も含めもう一度家庭での勉強環境の見直しをしたいと思います。
大変勉強になりました。
そして何より今中1の段階で聞いておいてよかったなと思いました。
今後ともご指導よろしくお願い致します。
本当に本日はお時間をたくさんいただきありがとうございました。
私も昔の勉強法だなと思います。
受験前は「過去問やってー」って言ってました。
子どもは「過去の問題は出ない!」と拒否してましたが…。
家ではあまり勉強している姿は見ませんが、苦手だった教科も受験前にはできるようになっていてびっくりしました。
中学生になると、課題も多いと聞いています。
今日帰ってから「ママはもう勉強は⁈って言わないからね」と宣言したので頑張って距離感保っていきたいと思います。
今後も宜しくお願い致します。
現代は、私たち親世代の時とは全く勉強法が異なる事を実感致しました。
上から押さえつけるのではなく、また放任放置をせず、伴走したいと思います。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
塾長のお話は分かりやすく、疑問に思う事がないので、すっーと内容が入ってきました。
あっと言う間の2時間でした。
現在息子は塾長の教えの通り、勉強を進めています。
勉強を始めた頃は、分からずイライラする事もあったり、親に頼って、自分の期待する反応が得られない時はイライラしたりする事がありました。
でも、今は親を頼る事なく、自分で考え計画的に進めていけるようになりました。
これが、自学力ですね。
凄い力です。
お話の中であった、自学力を育てる親になる為に、ほどよい距離感で見守り、一緒に考え、一緒に乗り越えてあげられるように心がけたいと思いました。
セミナー後に、子供と話し合いました。
子供と同じ方向に向かっている事で、良い親子関係を築く事にも繋がると実感しました。
このように学ぶ機会を与えて頂きありがとうございました。
子供は小学校低学年ですが、明らかに自分が受けてきた偏差値重視、暗記重視の教育とは異なる時代を生きていると実感しています。
自分の経験していない、これからの時代を生きる子供に、どのように接していくべきなのか分からずに悩んでいましたが、セミナーを受講して自分が何を目標として、どのように子育てをしていくべきかが明確になりました。
大学生になるまで後10年余り。限られた時間の子育てを目標を持ち続け後悔ないようにしたいです。
わかりやすいお話、ありがとうございました。
声かけのヒントや具体的な書籍を教えて頂き、これからそれを参考に子どもに並走していければと思います。
また、体験授業以降、家庭学習時間が親と5~10分だったのが、自分で1時間~1時間半するようになりました。
先生は90分の間に適度に危機感を持たせつつも、学ぶ楽しさまで教えるなんて、どんな声かけをしたのだろうと驚いています。
ありがとうございます。
学習習慣がこのまま継続するように環境の調整や声かけをセミナーからの学びを通して行動していけたらと思います。
期末テストが近づくとどうしても試験の為の勉強に気を取られてしまいます。
限られた期間だけ頑張っても身につかないのに今回もテストに気を取られていました。
普段から勉強体力をつけ、試験だけの勉強にならないようにしなければならないと本当に思います。
その為に自分で目標、課題を決めて頑張ってもらいたいです。
特に最近英語が苦手なようなので、きちんと何故間違えたか整理し見直すなど何とか工夫して勉強してもらえればと思います。