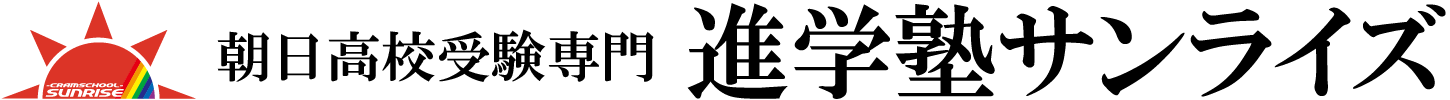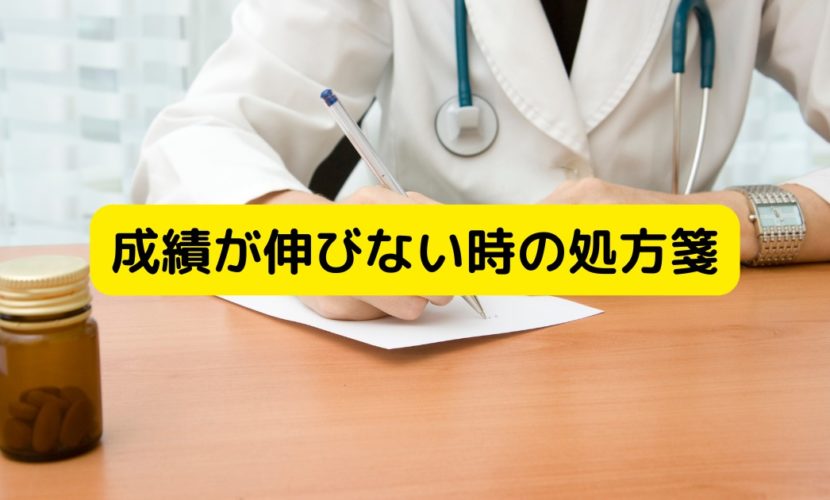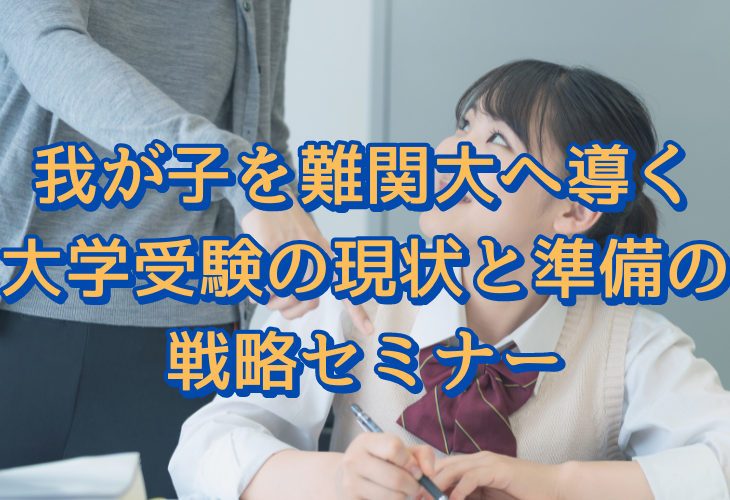塾通いで成績に差がつく?
昨年から続くコロナ禍での教育現場では、子どもたちの学習の進捗がテスト結果に表れていると聞きます。
端的には塾通いをしているかどうかが明暗を分けた、と明言する人もいました。
昨年のように登校できない期間はなかったものの、依然として学校外での勉強こそ実力を左右する大きな要因であることには間違いありません。
一度身についた勉強法は成功体験があるほど変えられない
長年子どもたちを指導していますが、開塾当初から同じ授業をしているわけではなく、時代の潮流に合わせて変えています。
学年によって多少の実力差や集団の特色もありますし、伸び悩みが見られたら勉強の仕方そのものを変える、という大胆な手法もとってきました。
以前、中学時代に偏差値70を維持していた子どもたちが、高校に上がった途端に急降下を始めてしまう、ということがありました。
朝日高校のような進学校に在籍していれば誰でも経験しうることですが、入試で選抜された上位成績者が集まる集団の中では、中学と同じような勉強をしていてもその中での上位に浮上することは容易ではありません。
打開するためには勉強法を見直す必要があるのですが、一度身についた勉強法というのはなかなか手放せないもの。
成功体験が過去のやり方に執着させてしまうのです。
子どもたちが自分の頭で考える余地を残す
そこで、思い切って授業のやり方を変えることにしました。
授業の中では概念・原理を詳しく解説して、他のどの勉強と関連しているのかもトークに盛り込みます。
要は基本を理解できるように仕向けるのです。
そして、その講義形式の授業と同程度の時間を演習に充てます。
加えて、一度解いた問題を私の前で「どうしてこの解になったのか?」を再現するプレゼンをしてもらうのです。
問題の難度がかなり高いので最初はなかなか出来ないのですが、徐々に解説を見て質問に来る塾生が増えてきました。
「どうしてこの解になるのか?」という疑問を持つようになったのです。
その後はクリアできた子が他の塾生に教えるなど、好循環の兆しが見えてきました。
それは、子どもたちが基礎を理解した上で自分たちの頭を使って考える力がついてきた、ということ。
この学年の塾生たちが後になってぐんぐん成績を伸ばしていったのは言うまでもありません。
基本を学ぶために教科書を活用しよう
以前は授業の中で、基礎を一通り講義した後に、応用問題についても解説していたのですが、最近は基礎が理解できていれば応用も自然とこなせることがわかってきました。
基礎が理解できている子たちは、複数の基礎的知識を組み合わせるなど、アイデアが湧いてくるようです。
こうした基本的なことをしっかり理解するために最適なのは学校の教科書です。
春休み、夏休み、冬休みといった長期休暇の家庭学習は、教科書を使った復習を中心に、基礎が本当に理解できているかどうかのチェックから行ってみることをお勧めします。