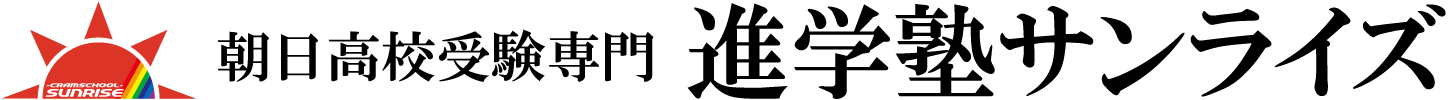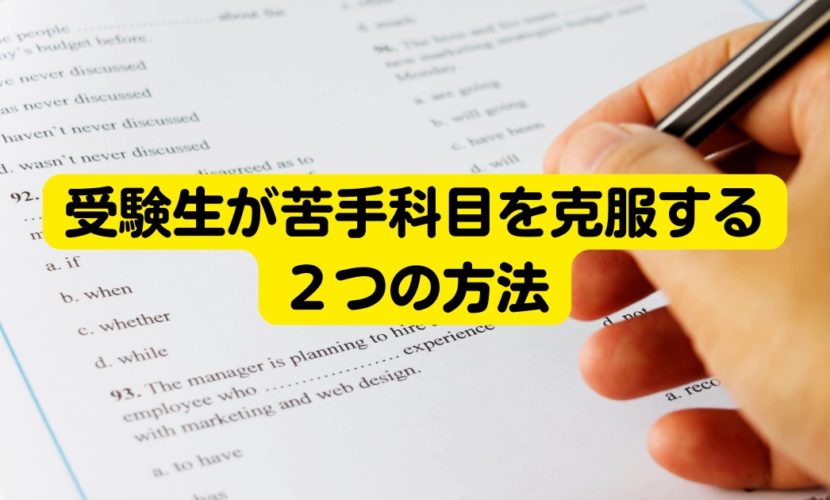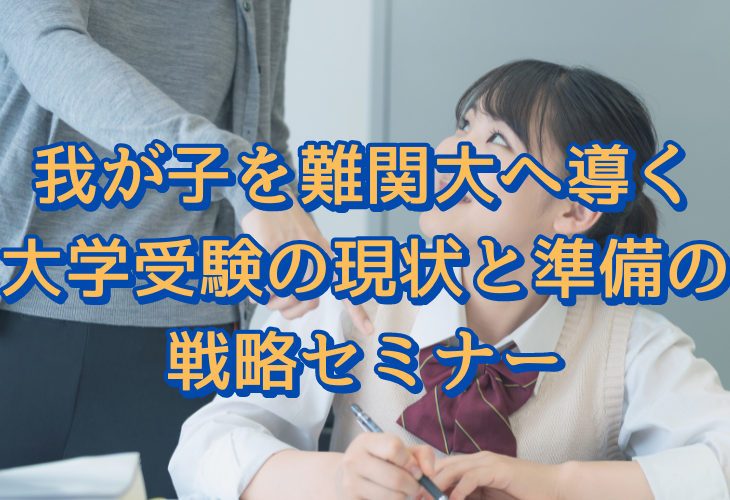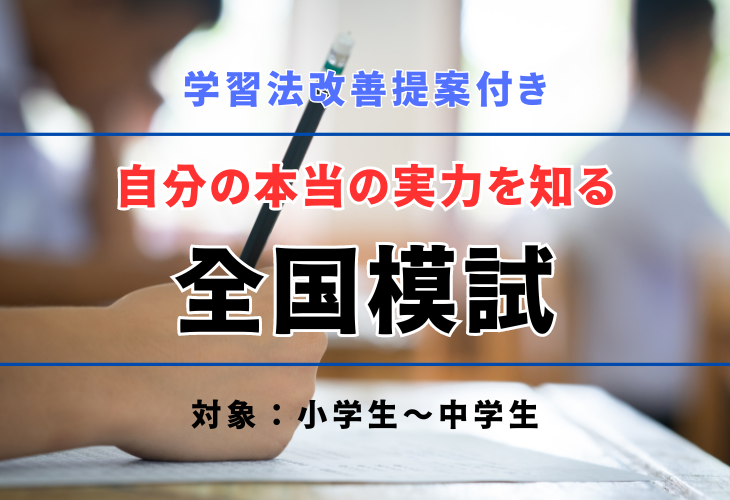8月度の模試の結果が返ってきたので、中3受験生に、今後の受験特訓のメニューを伝えました。
特に苦手科目がある場合、残りの期間で効率よく学習しないと、合格を逃してしまうかもしれません。
大抵の場合、子どもに勉強を任せてしまうと、テキストの1ページ目から始めたり、得意な単元からやろうとします。
本当にそれで伸びるのか、当の本人はそこまで考えていないのです。
テストの結果を良く見ると、間違えている問題から、特にできていない単元や分野が見えてくるはずです。
方程式なのか、図形なのか、物理なのか生物なのか、歴史なのか地理なのか、文法なのか、読解なのか・・・。
苦手を得意にするには、その科目のどの分野が苦手なのかをしっかり見極めることが必要です。
でも、それだけではいけません。
子どもによって、間違えた問題のレベルが違います。
基本的な問題か、応用的な問題かの見極めが必要となります。
基本が理解できていないのに、応用問題ばかりにチャレンジしていれば、いくら問題を解いても意味が理解できず、かえって遠回りになります。
ここで、苦手科目を克服する2つの方法です。
中1・中2用問題集を使う
もし、基本的な問題を多く間違えているようなら、その分野を学習する学年の通年用テキストを使用しましょう。
中1用の数学問題集、中2用の英語テキスト、といったものです。
説明も載っていますし、一から勉強し直せます。
できれば、2,3種類やるとよいです。
間違っても、1ページ目から順番に解かないでください。
苦手な単元だけ、です。
入試過去問集を使う
応用問題を多く間違えている人は、過去問集や実戦問題集を使いましょう。
おすすめは、「全国入試問題正解」(旺文社)です。
問題量が多く、入試に良く出るパターンの問題を豊富に解くことができます。
例えば、理科の生物分野の細胞分裂が苦手なら、その問題だけをピックアップして、解きまくってください。
同じような問題も出てきますから、徐々に正答率が上がってくるはずです。
苦手単元がたくさんある場合は、単元を絞る必要があります。
全部やりたい気持ちは分かります。
でも、時間は限られています。
全部が中途半端にならないように、苦手な順に優先順位をつけましょう。
一つずつ、確実に克服していく方が、何度もやり直しする必要がなくなるので、結局は近道になるのです。